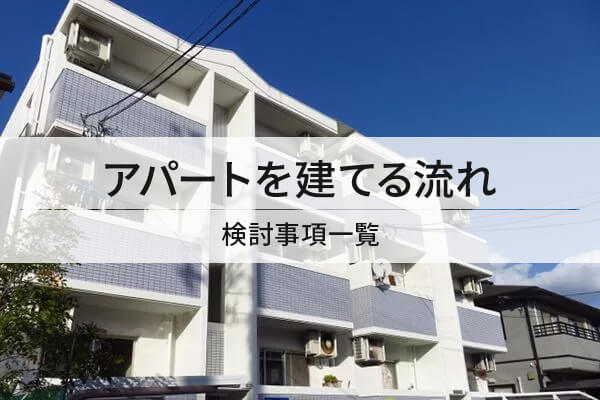アパート経営で節税できる?13の税金対策と節税事例集
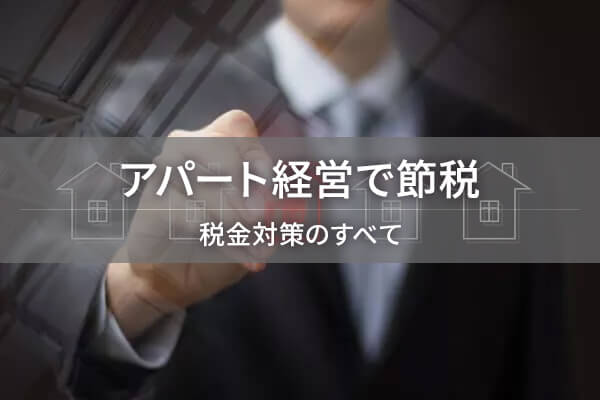
アパート経営は節税に効果的と聞いたことがある方は多いのではないでしょうか。実際、アパート経営は相続税対策に用いられるほか、経営する中で所得税や住民税、贈与税などに関しても節税効果が見込める様々な手法があります。
本記事では、アパート経営にかかわる税金とその算出方法について解説したうえで、節税対策について紹介します。
また、節税対策を含むアパート経営についてプロに直接相談したい方は以下のボタンから、経営プラン請求ができますので、ぜひご利用ください。
会社があります!

1.アパート経営で節税できる税金とできない税金
最初にアパート経営で発生する10種類の税金について紹介します。
| 税金 | 課税対象 | 算出方法 |
|---|---|---|
| 1.所得税 | 1年の不動産所得(家賃等)にかかる税 | 所得×累進課税率-控除額 |
| 2.住民税 | 1年の不動産所得(家賃等)をもとに計算される税 | 所得×10%+均等割 |
| 3.事業税 | 賃貸経営を事業としている場合に事業所得にかかる税 | (総収入金額-必要経費-290万円)×5% |
| 4.固定資産税 | 土地と建物にかかる市区町村税 | 課税標準×1.4% |
| 5.都市計画税 | 土地計画で指定されている市街化区域内の土地と建物にかかる税 | 課税標準×0.3% |
| 6.不動産取得税 | 不動産を取得(購入)した時にかかる都道府県民税 | 固定資産税評価額×3% |
| 7.登録免許税 | 不動産登記(名義変更等)の時に法務局に納める国税 | 固定資産税評価額×0.4% |
| 8.印紙税 | 建築工事の契約書などに印紙を貼り付ける | 請負金額による |
| 9.相続税 | 相続によって不動産など財産を取得した時にその財産にかかる税金 | 各相続人の取得金額×税率の合計額 ※税率は金額によって変動 |
| 10.贈与税 | 財産のもらった時にその財産にかかる税金 | 基礎控除後の課税価格×税率 ※税率は変動によって変動 ※贈与税には暦年課税と相続税精算課税がある |
このうち、アパート経営で節税ができる税目とできない税目について一覧にまとめました。
| できる/できない | 税目 | 節税対策に有効な方法や特例 |
|---|---|---|
| ○ | 所得税 | 減価償却や損益通算による節税 |
| ○ | 住民税 | 減価償却や損益通算による節税 |
| ○ | 事業税 | 経費の幅が広がることによる節税 |
| ○ | 固定資産税 | 住宅用地の軽減措置 |
| ○ | 都市計画税 | 住宅用地の軽減措置 |
| ◎ | 相続税 | 評価額の差異と貸家建付地による節税 |
| ◎ | 贈与税 | 特例贈与財産の税率適用による節税 |
| × | 不動産取得税 | ― |
| × | 登録免許税 | ― |
| × | 印紙税 | ※期間限定の軽減税率適用 |
※印紙税は租税特別措置法により2027年4月まで軽減措置(国税庁|不動産売買契約書の印紙税の軽減措置)
アパート経営でかかる税金はタイミングによって変わります。確定申告時、保有時、建築時(取得時)の3つのタイミングです。
それぞれの節税対策の仕組みは異なりますが、多くの税目では正当な手法で節税ができます。
1-1.消費税は免税事業者であれば納税義務はない
消費税は、免税事業者であれば納税義務はありません。
消費税を実際に国に納めるのは課税事業者と呼ばれる事業者です。課税事業者とは、年間の課税売上高が1,000万円を超える事業者を指します。それに対して、消費税の納税義務のない事業者を免税事業者と呼びます。
住宅の家賃は消費税が生じない課税売上であるため、アパート経営者は免税事業者であることが多いで免税事業者であれば消費税を納める必要がないため、「消費税の確定申告」は不要となります。
なお、アパート経営にかかる税金と節税について詳しく知りたい方は、以下の動画や関連記事も併せてご確認ください。
また、以下のボタンから土地の情報を入力すると、節税を考慮したアパート建築プランを、最大10社の建築会社から無料で取り寄せることができます。
会社があります!

2.アパート経営でできる13の税金対策
この章ではアパート経営でできる税金対策について解説します。税目によって対策方法は変わります。どの税目に有効な対策方法かをあわせてご確認ください。
2-1.税金対策に強いハウスメーカーに依頼すると多くの税目で節税効果が
アパートを建てるハウスメーカー選びはその後の収益計画を左右するといっても過言ではありません。税金について詳しいハウスメーカーを選ぶことで、発生する費用の何が必要経費になるか、支出を減らす工夫など、具体的なアドバイスをもらうことができます。
税制には小規模宅地の特例や貸家建付地などさまざまなものがあるため、条件に合わせて税金の軽減措置に適用させることも税金対策です。
またこのような税金についての相談を、アパートを建てた後でも無料で行ってくれるハウスメーカーもあります。
アパート経営の節税対策については「HOME4U(ホームフォーユー)土地活用」を使うと、最大10社のハウスメーカーから無料で節税対策を含む収支プランの提案を受けることができます。
2-2.【所得税・住民税】減価償却を上手に活用する
アパートの建築は構造選びも重要なポイントになります。
なぜなら構造によって法定耐用年数が異なり、減価償却できる期間が変わるからです。
減価償却費が計上できる期間は所得からその分を差し引けるため、節税効果があります。
減価償却費は、建物の建築費用を法定耐用年数の期間に分割で経費として計上できるものです。実際には支払っていないものの所得から差し引くことができるので、所得税と住民税の節税ができます。
減価償却費の計算方法についてはこちらで解説しています。
2-3.【所得税・住民税】青色申告特別控除
アパート経営で税金対策をするなら、青色申告を行うことが基本となります。
青色申告とは、正規の簿記の原則により記帳を行い、税務署長の承認を受ける記帳方法です。
青色申告を行うと、青色申告特別控除を適用することができます。
青色申告特別控除の控除額は、最高65万円又は10万円です。
10万円は10室未満のアパートの貸付を行っている場合に適用されます。10室以上のアパートの場合、青色申告特別控除額は、原則として55万円です。
ただし、以下の要件を満たすと、青色申告特別控除額は65万円となります。
【65万円の青色申告特別控除が受けられる要件】
イ.その年分の事業に係る仕訳帳及び総勘定元帳について、電子帳簿保存を行っていること。
ロ.その年分の所得税の確定申告書及び青色申告決算書の提出を、確定申告書の提出期限までにe-Taxを使用して行うこと。
2-4.【所得税・住民税】青色事業専従者給与
青色申告には、青色事業専従者給与を必要経費に算入できるというメリットがあります。
青色申告を行うと、「生計を一にする(日常生活において生活費をともにする)」15歳以上の配偶者その他の親族への給与を必要経費にすることができます。
青色事業専従者給与を行うには、10室以上のアパートであることが要件です。
一方で、白色申告(青色申告以外の申告のこと)では、事業専従者控除をすることができますが、その金額は配偶者なら86万円、その他の親族なら50万円までしか認められません。
そのため、金額が自由に設定できる青色事業専従者給与の方が節税対策として効果的です。
ただし、青色事業専従者給与は仕事に見合った給与でないと、否認されることがあります。
定期巡回や入出金管理等、実際に管理の仕事を行うことが必要です。
2-5.【所得税・住民税】管理会社の設立
管理会社の設立は、昔からあるオーソドックスな税金対策です。
複数物件を持っている場合には、トータルで物件を管理する立場の会社として自分の会社に管理を委託することができます。
私設の管理会社に管理委託料を支払うことで経費となり、かつ、その管理会社にお金を貯めていくことも可能です。
管理料としては、一般的には家賃収入の3~8%程度の間ですので、私設の管理会社への支払もその範囲に収める必要があります。
また、税務署は管理会社の管理実体も調査します。
管理実体としては、「入出金管理を行うこと」や「日報を残すこと」が必要です。
入出金管理は、各管理会社からバラバラに振り込まれている収入を、一旦、私設の管理会社の口座に振り込ませます。そこから管理料を差し引いた金額をアパートオーナーに振り込むという流れを作ることがポイントです。
ただし、私設の管理会社は、管理料が法外に高かったり、管理実体がなかったりすると、将来、税務調査が入ったときに管理料が過去に遡って否認される恐れがあります。
私設の管理会社は税金対策として有効ですが、しっかりとルールを守って行うようにしてください。
アパート経営の法人化について興味のある方はこちらもご覧ください。
2-6.【所得税・住民税】小規模企業共済
小規模企業共済とは、小規模企業の経営者や役員、個人事業主などのための、積み立てによる退職金制度です。
小規模企業共済は、掛金を全額所得控除できるので高い節税効果があります。
アパート経営においても小規模企業共済を利用することは可能です。
共済金は、退職・廃業時に受け取ることができ、退職金としてずっと貯金しておくことができます。
月々の掛金は1,000~70,000円まで500円単位で自由に設定することができますので、節税しながら将来のために貯金したい方にはおススメの税金対策となります。
2-7.【所得税・住民税】適切な修繕費の費用計上
節税のポイントは適切な修繕費を費用計上することです。
修繕費は原則として必要経費となりますが、その金額が大きいと資産として計上され、その期に一回で費用計上することができません。
例えば、アパートに1室追加するといった工事は、修繕というよりは増築といえます。
増築部分は修繕費ではなく建物資産となり、その後、減価償却の対象です。
支出が資産計上されてしまうお金のことを「資本的支出」と呼びます。
修繕費を費用として計上するには、資本的支出にならない範囲で金額設定することが必要です。
費用になるかどうかの判断には、以下のようなルールがあります。
- 建物の毀損部分の取り換え修理、畳の張り替え、外壁の塗替え
- 金額が20万円未満の改良や交換の費用
- おおむね3年以内の周期で行う修理
- 区分がしにくい場合は、金額が60万円未満かその資産の前期末の取得価額のおよそ10%以下
費用として認められる支出は、原則として20万円未満の支出です。
20万円以上の修繕は資本的支出とみなされます。
ただし、例外もあります。
例えば上記の費用として計上できるものの中に、「外壁の塗替え」があります。
外壁塗装は金額が大きいですが、一回で費用として落とせるため、その年の税金を大幅に圧縮することが可能です。
ただし、外壁塗装もバリューアップするような塗装が行われるときは、一部資産計上されてしまうことがあります。
また、修繕費に関しては、工事が終了し、引渡が済んでいれば未払いであってもその修繕費を費用計上することが可能です。
例えば、10万円の給湯機交換の工事が12月末に終わり、翌月の1月末までに支払うようなケースでは、10万円の給湯機交換費を12月末までの費用とすることができます。
修繕費は金額が大きいので、費用となるかならないかをしっかり税理士や管理会社等に確認した上で行うようにしてください。
2-8.【所得税・住民税】諸経費の費用計上
アパートの必要経費には、通信費や交通費、水道光熱費、接待交際費、新聞図書費、消耗品費等の諸経費があります。これらの費目は家事消費と混同されやすいものばかりですが、事業に必要なものであれば費用として計上することが可能です。
例えば、自宅を不動産賃貸業の事務所として使っている場合、その事務所スペース部分の水道光熱費を費用として計上できるほか、プリンター用紙代やインク代は消耗品費となります。
ゴルフや外食代も不動産投資のための情報交換の場であれば接待交際費、お中元やお歳暮も不動産賃貸業のために行っているものであれば接待交際費です。
ただし、これらの諸経費は家事消費と混同されやすいので、領収書等の証拠資料をしっかりと残しておくことがポイントです。事業に要した支出は普段からマメに領収書を取る癖をつけるようにしてください。
アパート経営でかかる経費についてはこちらでご確認ください。
2-9.【所得税・住民税】赤字が出た場合の損益通算
不動産所得は総合課税方式ですが、逆に不動産所得が赤字となった場合には他の所得にマイナスを合算し、全体の所得を少なくすることも可能です。
このようなプラスの所得とマイナスの所得を合算することを損益通算と呼びます。
例えば、給与所得が800万円で、不動産所得が▲200万円の場合、損益通算により全体所得が600万円となるため、給与所得の800万円を前提に会社が源泉徴収していた所得税の一部を取り戻すことができます。
そのため、マイナスの不動産所得があることで、全体の税金対策が可能です。
不動産所得のマイナスとは解せないかもしれませんが、例えば新築初年度は登録免許税や入居者募集の仲介手数料等が発生することもあり赤字となってしまうことが良くあります。
初年度の赤字になりやすい性質をうまく利用すると、損益通算によって税金全体の負担を減らせます。
2-10.【相続税】アパートを新築して借入金を作る
相続税は、土地だけでなく金融資産や現金など被相続人の遺産すべてが課税対象になります。
このとき、アパートローンなどの借入金も遺産としてカウントされるため、遺産総額から借入金をマイナスすることで相続税評価額を減らすことで相続税の節税が可能です。
2-11.【相続税】借地権割合と借家権割合が適用される
相続した土地でアパート経営をしている場合はその土地が貸家建付地となって、土地を自己都合で扱えないことから土地の評価額が下がります。
元々の土地評価額に借地権割合や借家権割合を乗じる仕組みです。
借地権割合は地域によって30%~90%に設定されています。借家権割合は30%固定です。この割合を計算式に用いることで、相続税評価額はかなり抑えられます。
よって、更地で相続するより、賃貸物件を建てた土地のほうが相続税負担を減らすことが可能になります。
相続税対策についてもっと知りたい方はこちらもご覧ください。
2-12.【贈与税】特例贈与財産の活用
贈与税は相続税より税率が高く設定されていますが、生前贈与をうまく活用することで相続税対策ができます。
贈与税でも相続税同様、課税対象の土地の評価額は現金よりも下がるため、特に貸家建付地であれば現金の贈与よりも節税が可能です。また、特例贈与財産用の税率を適用することも有効です。
特例贈与財産とは、祖父母や父母といった直系尊属から20歳以上の子や孫への贈与のことで、適用税率が異なります。
例えば、基礎控除(110万円)後の課税価格が3,000万円の贈与に対し一般贈与では50%の税率が適用されるのに対し、特例税率であれば45%です。
ただし、生前贈与は相続税対策との兼ね合いも重要なため、どの手段をどの程度とるのかをしっかり検討する必要があります。
参考:国税庁|No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)
2-13.【固定資産税・都市計画税】住宅用地の軽減措置が適用される
住宅用地の軽減措置は土地の評価額に対しての特例になるため、固定資産税、都市計画税など土地にかかる税金に対して大きな節税効果を発揮します。
この特例を受けるには条件があり、小規模住宅用地と一般住宅用地の2つの条件では軽減措置の幅が異なります。
| 小規模住宅用地 | 一般住宅用地 |
|---|---|
| 住宅やアパート用の敷地で戸数×200平米までの部分 | 住宅やアパート用の敷地で小規模住宅用地以外の土地 |
| 固定資産税:課税価格×1/6 都市計画税:課税価格×1/3 |
固定資産税:課税価格×1/3 都市計画税:課税価格×2/3 |
アパートの場合はワンルームも1戸と換算されるため、小規模住宅用地の要件が適用されることが多いでしょう。これから新築する場合はこの条件も加味して計画を立てることをおススメします。
固定資産税・住宅用地の特例についてはこちらで詳しく解説しています。
3.アパート経営関連の税金の節税事例集
この章ではアパート経営にかかる税金での税金対策について、詳しい例をもって紹介します。
対策しなかった場合との比較で、どの対策がどの程度の効果を発揮するのかがわかる内容です。
3-1.不動産所得の税金対策例
3-1-1.所得税の計算
不動産所得=収入金額-必要経費
課税標準=総所得金額
=給与所得+不動産所得+・・・+事業所得
所得税額=課税標準×税率-控除額
総合課税方式の税率は、所得が大きくなるほど税率が高くなる累進課税率です。
所得税の累進課税率および控除額は以下の通りです。
| 課税される所得金額 | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 195万円未満 | 5% | 0円 |
| 195万円以上330万円未満 | 10% | 97,500円 |
| 330万円以上695万円未満 | 20% | 427,500円 |
| 695万円以上900万円未満 | 23% | 636,000円 |
| 900万円以上1,800万円未満 | 33% | 1,536,000円 |
| 1,800万円以上4,000万円未満 | 40% | 2,796,000円 |
| 4,000万円以上 | 45% | 4,796,000円 |
上記の税率でそれぞれ計算し、さらに2037年までは「所得税」に対して一律2.1%をかけた金額が「復興特別所得税」として納税額にプラスされます。
また、住民税率は所得の大小に関係なく、一律約10%の税率がかかります。
3-1-2.所得税対策の事例
例えば、給与所得控除後の給与所得が800万円、不動産所得が500万円の場合、課税標準は1,300万円となるため、税率は「900万円超1,800万円以下」の33%、控除額は1,536,000円ということになります。
<条件>
給与所得:800万円(源泉徴収票の給与所得控除後の金額)
不動産所得:500万円
その他の所得:なし
<計算式>
課税標準=給与所得+不動産所得
=800万円+500万円
=1,300万円
所得税=1,300万円×33%-153.6万円
=275.4万円
復興特別所得税=所得税×2.1%
=275.4万円×2.1%
≒5.7万円
住民税=課税標準×10%+均等割
=1,300万円×10%+5,000円
=130.5万円
税金=所得税+復興特別所得税+住民税
=275.4万円+5.7万円+130.5万円
=411.6万円
この411.6万円が一般的な課税額です。
こちらの税金計算に税金対策として
- 修繕費積み立てを年額15万円
- 月に1万円の諸経費
をきっちり計上するとします。
その場合の上記との税額の差異は以下のようになります。
| 所得税 | 復興特別所得税 | 住民税 | 税金 | |
|---|---|---|---|---|
| 対策前課税額 | 275.4万円 | 約5.7万円 | 130.5万円 | 411.6万円 |
| 対策後課税額 | 約266.5万円 | 約5.6万円 | 127.8万円 | 約399.9万円 |
| 差額 | 8.9万円 | 1,000円 | 2.7万円 | 11.7万円 |
所得税、住民税などは毎年かかる税金です。
長期運用が基本のアパート経営では経費の計上が積もり積もって大きな影響を及ぼします。
アパート経営の経費について詳しく知りたい方はこちらも参考にしてください。
3-2.相続税の税金対策例
3-2-1.相続税の税金計算
純資産額価額=相続や遺贈で各人が取得した財産から非課税財産、債務などを差し引いた額
純資産価額+相続開始前3年以内の贈与財産の価額=各人の課税価額
各人の課税価額の合計-基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)=課税遺産総額
課税遺産総額×各法定相続人の法定相続分=各法定相続人の取得金額
各法定相続人の取得金額×税率=各人の相続税額
上記の計算式で求めた各法定相続人の相続税額を合計すると相続税の総額が算出できます。
相続税の税率は、以下の通りです。
| 相続税の課税標準 | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 1,000万円以下 | 10% | ― |
| 3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
| 5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
| 1億円以下 | 30% | 700万円 |
| 2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
| 3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
| 6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
| 6億円超 | 55% | 7,200万円 |
引用:国税庁|No.4155 相続税の税率
相続税の計算が難しいのは、土地などの相続財産の評価額の算出が素人では難しいためです。
土地などが絡む相続税計算は専門家の力を借りるとよいでしょう。
3-2-2.相続税対策の事例
ここでは計算を平易にするため更地(相続税評価額6,000万円)のみを相続財産として、子1人がそのまま相続する場合とアパートを建築する場合の対策効果を比較してみます。
<条件>
相続財産:更地(相続税評価額:6,000万円)
法定相続人:子1人
遺言書:なし
<計算式>
各人の課税価額の合計-基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)=課税遺産総額
6,000万円-3,600万円=2,400万円
法定相続人が1人のため、相続税の課税標準も2,400万円
2,400万円×15%(税率)―50万円(控除額)=310万円
更地にアパートを建てた場合、貸家建付地となり借地権割合を乗じると土地の相続税評価額が変わります。
アパートは満室状態、土地の借地権割合は60%としての計算です。
| 土地の評価額 | 相続税額 | |
|---|---|---|
| 更地 | 6,000万円 | 310万円 |
| アパートのある土地 | 4,920万円 | 148万円 |
| 差額 | 1,080万円 | 162万円 |
土地の相続税対策の効果を比較しましたが、実際には建物も相続財産となるほか、建物を建てたときの借入金が相続財産を減らす効果もあります。
相対的に見ると更地で相続するより賃貸物件を建てた土地を相続するほうが相続税対策としては効果的です。
3-3.固定資産税の税金対策例
3-3-1.固定資産税の税金計算
課税標準額とは、自治体の基準を用いて評価した土地の評価額です。時価のおおよそ7割程度とされています。
1.4%の税率は、多くの自治体で採用されている税率です。一部、自治体によってはこれよりも高い税率をかけている場合もあります。
このほか、エリアによっては都市計画税もかかります。税率は0.3%(制限税率)です。
3-3-2.固定資産税の税金対策例
固定資産税で節税効果のある対策には住宅用地の特例を用います。
ここでは土地のみにフォーカスして、更地での固定資産税とアパートの敷地の固定資産税で節税効果を確認します。
土地の課税標準額(固定資産税評価額)は6,000万円での資産です。
標準課税額:6,000万円
土地の状態:更地(賃貸契約なし)
課税標準額×1.4%(税率)=固定資産税額
6,000万円×1.4%=84万円
次に同じ条件の土地にアパートがある場合を計算し、税額の差分を求めます。
住戸が8戸で敷地面積が330平米の土地で、小規模住宅用地の適用が受けられる想定です。
小規模住宅用地の場合、課税標準額に1/6をかけた額を基に計算します。
| 土地の評価額 | 固定資産税額 | 都市計画税額 | |
|---|---|---|---|
| 更地 | 6,000万円 | 84万円 | 6万円 |
| アパートのある土地 | 1,000万円 | 14万円 | 約1万円 |
| 差額 | 5,000万円 | 70万円 | 約5万円 |
固定資産税は毎年かかる税金ですが、年額で70万円の差が出ます。
固定資産税は建物にもかかる税金のためアパート自体にも課税がありますが、収益物件ですから更地で税金を納め続けることを考えるとアパートを建てたほうが節税になります。
アパート経営の税金についてもっと知りたい方はこちら
4.アパート経営の税金対策に合ったハウスメーカーの見つけ方
アパート経営は始める時から税金対策を念頭において計画する必要があります。
軽減措置の特例などの適用を受けるには土地や建物に条件があるため、建築計画段階から税金対策に知見あるハウスメーカーをパートナーに選出しなければなりません。
そこで、活用したいのが「HOME4U 土地活用」です。大手ハウスメーカーには税金対策に精通したスタッフがおり、土地の特徴にマッチしたプランを提案できます。
会社があります!

アパート経営で節税のために対策できる税金は以下の7つの税目です。
- 所得税
- 住民税
- 事業税
- 固定資産税
- 都市計画税
- 相続税
- 贈与税
節税できる税目とできない税目の一覧を「アパート経営で節税できる税金とできない税金」でまとめています。をご一読ください。
所得税と住民税は、アパート経営の中でもコツコツと税金対策ができる税目です。以下のような対策方法があります。
- 減価償却を上手に活用する
- 青色申告特別控除
- 青色事業専従者給与
- 管理会社の設立
- 小規模企業共済
- 適切な修繕費の費用計上
- 諸経費の費用計上
- 赤字が出た場合の損益通算
詳しくは「アパート経営でできる税金対策」でご確認ください。
アパート経営は土地活用の中でも最も有効な相続税対策です。具体的には以下のような面が対策として活用できます。
- アパートを新築して借入金を作る
- 借地権割合と借家権割合の適用が受けられる
どのような仕組みで節税になるかは「アパート経営でできる税金対策」で解説しています。
-
【基本を解説】知識ゼロから始める「アパート経営 基本ガイド」 アパート経営は土地活用の王道ともいえる、人気の高い活用方法です。こちらの記事では、アパート経営で相続税対策をする方法や具体的な収益シミュレーションを確認することができます。
アパート経営の収益・節税プランを企業に請求できます!
電話でもプラン請求をお受けします。「個人情報の取り扱いについて」に同意の上、お電話ください。


![[19周年]利用者数1,000万人[HOME4U年間利用者数2020年5月現在]](/img/common/header_f1.jpg)