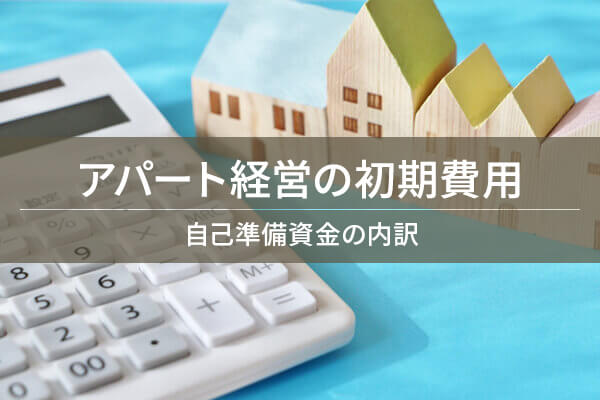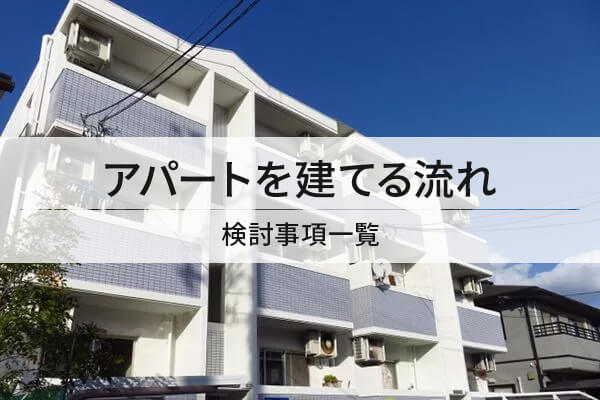ここではアパート経営を始めるにあたって必要な初期費用を解説します。
下記は、建設費を除いた必要な初期費用の費用項目をまとめた表になります。
アパート経営開始に必要な、建設費以外の初期費用項目 一覧
| 支出のタイミング |
費用項目 |
目安 |
| 計画時に必要な費用 |
現況測量費 |
30万円程度 |
| 地盤調査費用 |
1ポイント50万円程度 |
| 建物解体費 |
木造なら坪4~5万円 |
| 請負契約・着工時に必要な費用 |
建築費 |
木造なら坪単価77万~100万円 |
| 印紙代 |
5,000万円超1億円以下なら6万円 |
| 設計料 |
工事費の1~3% |
| 水道分担金 |
100万円~500万円 |
| 奉献酒 |
5,000円 |
| 工事期間中の費用 |
土地の固定資産税および都市計画税 |
2階建てなら3ヶ月分 |
| 追加工事 |
必要に応じて発生 |
| 竣工時に必要な費用 |
火災・地震保険料 |
1年分は請負工事金額の0.05%程度 |
| 新築建物登録免許税 |
固定資産税評価額×0.4% |
| 抵当権設定登記費用 |
債権金額×0.4% |
| 司法書士手数料 |
6~7万円程度 |
| 新築建物不動産取得税 |
固定資産税評価額×3%が基本 |
| 融資関連費用 |
事務手数料だけなら5~10万円 |
| 入居者募集費用 |
家賃保証型ではない場合 |
賃料の1ヶ月 |
| 家賃保証型の場合 |
賃料の3~6ヶ月 |
アパート経営開始に必要な、建設費以外の初期費用項目 一覧
| 計画時に必要な費用 |
| 現況測量費 |
30万円程度 |
| 地盤調査費用 |
1ポイント50万円程度 |
| 建物解体費 |
木造なら坪4~5万円 |
| 請負契約・着工時に必要な費用 |
| 建築費 |
木造なら坪55~80万円 |
| 印紙代 |
5,000万円超1億円以下なら6万円 |
| 設計料 |
工事費の1~3% |
| 水道分担金 |
100万円~500万円 |
| 奉献酒 |
5,000円 |
| 工事期間中の費用 |
| 土地の固定資産税および都市計画税 |
2階建てなら3ヶ月分 |
| 追加工事 |
必要に応じて発生 |
| 竣工時に必要な費用 |
| 火災・地震保険料 |
1年分は請負工事金額の0.05%程度 |
| 新築建物登録免許税 |
固定資産税評価額×0.4% |
| 抵当権設定登記費用 |
債権金額×0.4% |
| 司法書士手数料 |
6~7万円程度 |
| 新築建物不動産取得税 |
固定資産税評価額×3%が基本 |
| 融資関連費用 |
事務手数料だけなら5~10万円 |
| 入居者募集費用 |
| 家賃保証型ではない場合 |
賃料の1ヶ月 |
| 家賃保証型の場合 |
賃料の3~6ヶ月 |
>アパートの建築費用が気になる人はこちら→建築費シミュレーション
>ローンの返済スケジュールが気になる人はこちら→ローン返済シミュレーション
この記事では、これらの費用項目を詳しく解説していきます。
また、具体的なアパート経営の初期費用について相談したい方は、以下のボタンから建築プランを取り寄せられます。ぜひご利用ください。
1.アパート経営初期費用のおよその目安
アパートを建てる際、建築費以外でかかる初期費用は、全体の「5%程度」が目安となります。
アパートの初期費用は、アパートの建築プランや請負工事費が決まらないと正確な数字が見えてこない費用も少なくありませんが、とりあえず5%程度を予備費として持っておくことがアパート建築の基本です。
例えば7,000万円のアパートを建てる場合は、5%である350万円程度の予備費が必要となります。
新築アパートを建てる場合には、余裕を持った状態で始めるようにしましょう。
アパート建築の初期費用がどの程度で回収できるか知りたい方は「HOME4U(ホームフォーユー)土地活用」をご利用ください。最大10社から具体的な収支プランが手に入れられます。
アパートを建築した時の予想収益はいくら?
2.アパート建築計画時に必要な費用3つ
最初に、計画時に必要な下記3つの費用について解説します。
2-1.現況測量費
設計を行うには、土地の実測図が必要です。
既に実測図がある場合には、それをハウスメーカーに渡してください。
既存の実測図の内容で十分であれば、測量は不要です。
測量図がない場合には、測量を行います。測量は、あくまでも設計のための実測図なので、境界まで確定する必要はありません。
設計で必要な測量図は、現況測量図と呼ばれます。現況測量図は、一般的に隣地境界の立会いを経ずに測量した図面を指します。
現況測量図(作成)の費用は、30万円程度です。
尚、測量では真北測量や高低測量も必要となる場合があります。無駄を防ぐためにも、測量は設計者の指示を仰いでから行うようにして下さい。
2-2.地盤調査費用
地盤調査とは、杭工事が発生する場合に、支持地盤の深さを測る調査のことです。
杭工事が発生しない場合には、地盤調査費用は不要です。
基本的には2階建てアパートなら杭工事はないことが多いので、地盤調査費用は発生しないことが一般的です。
ただし、地盤の弱い場所や3階建以上アパート、重量鉄骨または鉄筋コンクリート造などの重量の重いアパートを作る場合は、杭工事が必要となってくるケースがあります。
地盤調査費用は、1ポイント当たり50万円程度の費用がかかります。
広い土地で大きなアパートを建築する場合は、2ポイント以上必要となることもあります。
地盤調査会社は、ハウスメーカーによっては、依頼すると複数社の相見積を取ってくれることもあります。
2-3.建物解体費
土地の上に既存建物が残っている場合には、建物解体費が発生します。
解体費用の坪単価の目安としては以下の通りです。
構造別 解体費坪単価の相場一覧
| 木造 |
坪4~5万円 |
| 軽量鉄骨造 |
坪6~7万円 |
| 鉄筋コンクリート造 |
坪7~8万円 |
例えば、50坪の木造アパートが建っている場合には、200万円から250万円の解体費用が発生することになります。
3.アパート建築工事請負契約・着工時に必要な費用5つ
この章では請負契約または着工時に必要な下記5つの費用について解説します。
3-1.建築費
建築費は、構造や規模によって異なります。概算のために、以下の坪単価の相場をご参照ください。
アパート構造別 建築費坪単価の相場
| 木造 |
55~80万円 |
| 鉄骨造 |
80~120万円 |
| 鉄筋コンクリート造 |
90~120万円 |
具体的な建築費の相場については、以下のシミュレーションから確認可能です。
より詳しいアパートの建築費の詳細は、以下の動画や関連記事も併せてご確認ください
また、以下のボタンから土地の情報を入力すると、あなたの土地にあったアパートの建築費の見積もりを、最大10社の建築会社から無料で取り寄せることができます。
3-2.印紙代
ハウスメーカーと締結する請負う工事契約書には印紙を貼ります。
印紙税は請負工事金額によって、以下のように定められています。
契約金額と印紙税の対照表
| 記載された契約金額 |
税額 |
| 1万円未満のもの |
非課税 |
| 1万円以上 100万円以下のもの |
200円 |
| 100万円を超え 200万円以下のもの |
400円 |
| 200万円を超え 300万円以下のもの |
1,000円 |
| 300万円を超え 500万円以下のもの |
2,000円 |
| 500万円を超え 1,000万円以下のもの |
1万円 |
| 1,000万円を超え 5,000万円以下のもの |
2万円 |
| 5,000万円を超え 1億円以下のもの |
6万円 |
| 1億円を超え 5億円以下のもの |
10万円 |
| 5億円を超え 10億円以下のもの |
20万円 |
| 10億円を超え 50億円以下のもの |
40万円 |
| 50億円を超えるもの |
60万円 |
| 契約金額の記載のないもの |
200円 |
3-3.設計料
設計料に関しては、以前は工事費に料率を乗じて求める方法が主流でしたが、現在では延床面積を基準に求めるのが主流です。
ただし、延床面積を基準に設計料を求める方法は、施工会社とは別の外部の設計会社に依頼した場合であり、ハウスメーカーにアパート建築を依頼した場合の設計料は、ハウスメーカー独自の基準で算出されます。
ハウスメーカーのように設計会社と施工会社が一体となっている場合を、「設計施工一貫方式」と呼びます。
ハウスメーカーの設計施工による設計料は、非常に安いのが特徴です。
設計料は、請負工事の見積書の内訳の中に記載されていますが、設計料は工事費全体の中で1~3%程度となっています。
外部の設計会社に依頼すると、設計料は工事費に対して7~8%程度になることもありますが、ハウスメーカーに依頼した場合には極端に安くなるため、アパート建築はハウスメーカーの設計施工を選択するのが通常です。
設計施工一貫方式を採用する大手ハウスメーカーが多く参画する「HOME4U(ホームフォーユー)土地活用」を活用すれば、最大10社の大手ハウスメーカーの建築プランが簡単に無料で手に入れられます。
アパートの建築費や将来の収益はいくら?
大手10社のプラン比較はコチラから!
3-4.水道分担金
水道分担金とは、水道の利用申込に際して自治体の水道局に納付しなければならないお金です。
アパートなどの集合住宅を作る場合、複数戸に水道を供給しなければならないため、引込の口径を太くする工事をしなければなりません。
水道分担金は、引込の水道管の口径を太くする場合に必要となります。
金額は、口径が太くなるほど高くなり、場合によっては100万円~500万円程度の金額が生じます。
口径はアパートの戸数が多くなると太くする必要があるため、戸数の多いアパートは水道分担金が高くなる傾向があります。
水道分担金は金額が大きく、驚くアパートオーナーも多いのですが、自治体に支払う金額であるため、値引きや減額ができません。
水道分担金はハウスメーカーが事前に調べてくれます。
3-5.奉献酒
アパートは、着工時に地鎮祭を行うのが通常です。
地鎮祭とは、基礎工事にかかる前に土地の神を祭り、工事の無事を祈る祭事のことを指します。
ちなみに、地鎮祭は施工者からの「お願いします」という式典なので、神主等の費用はハウスメーカーが負担します。
地鎮祭では、アパートオーナーも奉献酒と呼ばれるお酒を持参します。
奉献酒の相場は1升瓶2本で5,000円程度です。
のし紙にアパートオーナーの名前を書くのを忘れないようにしましょう。
4.アパート工事期間中の費用
この章ではアパート建築工事期間中の下記2つの費用について紹介します。
4-1.土地の固定資産税および・都市計画税
工事中においても土地の固定資産税および都市計画税は発生します。
アパートの工期は2階建てだと3ヶ月程度ですが、工事中は駐車場などの収益を上げることはできないため、その間の固定遺産税の負担感は大きくなります。
工事中はアパートが建ってないため、固定資産税は更地と同じ高い課税のままです。
翌年の1月1日時点にアパートが竣工(工事が完了していること)していると、住宅用地の軽減措置の特例を適用できるため、翌年からの土地の固定資産税は安くなります。
土地に建物をたてた際の節税額はいくら?
固定資産税について、詳しくは、こちらの記事を参考にしてみてください。
4-2.追加工事
追加工事とは、着工後に発生する請負工事以外の想定外工事になります。
追加工事は基本的には無いのですが、工事をしてみて「やっぱりここは、こうした方が良いのでは?」という部分が発生すると、追加工事費が発生します。
例えば、計画中にバイク置き場や宅配ボックスの設置を想定しておらず、工事が始まったら「やっぱりここにバイク置場を作ろう」となる場合があります。
図面だけだと、どうしても想像力が働かないため、工事現場を見ると急に必要な工事が思いつく場合があります。
もし、工事期間中のやるべき追加工事を思いついたら、追加工事費用を払って工事を実行することをおススメします。
工事中は、職人が他の工事のついでに追加工事を行ってくれるため、竣工後に別途工事をするよりも安くなります。
また、他の工事を削って、追加工事費用を捻出できることもあるため、追加コストを抑えることもできます。
工事を着工する際は、追加工事費が発生するかもしれないという心構えだけはしておいた方が良いでしょう。
5.アパート竣工時に必要な費用6つ
この章ではアパート竣工時に必要な下記6つの費用について解説します。
- 火災・地震保険料
- 新築建物登録免許税
- 抵当権設定登記費用
- 司法書士手数料
- 新築建物不動産取得税
- 融資関連費用
5-1.火災・地震保険料
火災保険や地震保険の保険料は、本来、毎年の費用として発生するものです。
しかしながら、火災保険等は長期一括で加入した方が安いことから、初年度に数年分を加入するケースも多いです。
火災保険は複数年の一括契約をする際は、単純に何年分というわけではなく、以下のような長期係数が乗じられて保険料が決まります。
一例を示すと以下のようになります。
| 保険期間 |
長期係数 |
| 2年 |
1.85 |
| 3年 |
2.70 |
| 4年 |
3.50 |
| 5年 |
4.30 |
| 6年 |
5.10 |
| 7年 |
5.90 |
| 8年 |
6.70 |
| 9年 |
7.45 |
| 10年 |
8.20 |
1年分の保険料は、概算値として新築の請負工事金額の0.05%を乗じて求めます。
8,000万円の工事費であれば、年間保険料は約4万円(=8,000万円×0.05%)です。
例えば、5年分の保険料を一括契約する場合は、長期係数4.30を用いると、17.2万円(=4万円×4.30)と計算されます。
5-2.新築建物登録免許税
登録免許税とは、登記を行うために法務局に支払う税金です。
一旦、登録免許税を司法書士に預け、司法書士が法務局へ代理で支払うことが通常です。
建物を新築したときに行う登記は、「表示登記」と「所有権保存登記」の2つです。
表示登記とは、不動産登記の表題部にされる登記のことを指しますが、表示登記の登録免許税は不要です。
一方で、所有権保存登記とは、新たに生じた不動産について初めて行なわれる所有権の登記のことを指します。
新築建物の登録免許税は、以下の計算式で計算されます。
登録免許税=課税標準額(固定資産税評価額)×0.4%
固定資産税評価額については、新築工事費の概ね50~60%程度となります。例えば、アパートの新築請負工事費が4,000万円だとしたら、建物の固定資産税評価額は2,000万円~2,400万円程度です。仮に、固定資産税評価額が2,000万円の場合、登録免許税は以下のように計算されます。
登録免許税=固定資産税評価額×税率 固定資産税評価額が2,000万円の場合:2,000万円×0.4%=8万円
5-3.抵当権設定登記費用
アパートローンを組んだ場合、土地と建物に抵当権の設定登記を行います。
抵当権とは、ローンを返済できなくなった場合、銀行が優先的に弁済を受けることができるための権利です。
競売時の担保価値を維持するためにも抵当権は土地と建物に設定することが通常です。
抵当権設定登録免許税は、以下の計算式で計算されます。
登録免許税=課税標準額(債権金額)×0.4%
例えば4,000万円のアパートローンを組んだ場合の登録免許税は以下のように計算されます。
登録免許税=債権金額×税率 例)4,000万円のアパートローンを組んだ場合の登録免許税 4,000万円×0.4%=16万円
5-4.司法書士手数料
建物の所有権保存登記や抵当権設定は、司法書士に依頼するため、司法書士手数料が発生します。
日本司法書士連合会の「報酬アンケート結果一覧(2013年〔平成25年〕2月実施)」により、司法書士手数料の目安を示します。
まず、課税価格1,000万円の新築建物の所有権保存登記手続の代理業務を受任した場合、「所有権保存登記」にかかる金額は以下のようになっています。
地区別 課税価格1,000万円の新築建物の所有権保存登記手続 手数料相場一覧
| |
低額者10%の平均 |
全体の平均値 |
高額者10%の平均 |
| 北海道地区 |
12,232円 |
18,272円 |
25,300円 |
| 東北地区 |
11,627円 |
20,558円 |
33,668円 |
| 関東地区 |
12,663円 |
22,152円 |
47,813円 |
| 中部地区 |
15,206円 |
22,427円 |
31,182円 |
| 近畿地区 |
13,833円 |
29,607円 |
64,000円 |
| 中国地区 |
14,537円 |
23,751円 |
34,200円 |
| 四国地区 |
14,555円 |
23,661円 |
36,667円 |
| 九州地区 |
13,087円 |
22,016円 |
41,500円 |
地区別 課税価格1,000万円の新築建物の所有権保存登記手続 手数料相場一覧
| 北海道地区 |
| 低額者10%の平均 |
12,232円 |
| 全体の平均値 |
18,272円 |
| 高額者10%の平均 |
25,300円 |
| 東北地区 |
| 低額者10%の平均 |
11,627円 |
| 全体の平均値 |
20,558円 |
| 高額者10%の平均 |
33,668円 |
| 関東地区 |
| 低額者10%の平均 |
12,663円 |
| 全体の平均値 |
22,152円 |
| 高額者10%の平均 |
47,813円 |
| 中部地区 |
| 低額者10%の平均 |
15,206円 |
| 全体の平均値 |
22,427円 |
| 高額者10%の平均 |
31,182円 |
| 近畿地区 |
| 低額者10%の平均 |
13,833円 |
| 全体の平均値 |
29,607円 |
| 高額者10%の平均 |
64,000円 |
| 中国地区 |
| 低額者10%の平均 |
14,537円 |
| 全体の平均値 |
23,751円 |
| 高額者10%の平均 |
34,200円 |
| 四国地区 |
| 低額者10%の平均 |
14,555円 |
| 全体の平均値 |
23,661円 |
| 高額者10%の平均 |
36,667円 |
| 九州地区 |
| 低額者10%の平均 |
13,087円 |
| 全体の平均値 |
22,016円 |
| 高額者10%の平均 |
41,500円 |
また、土地1筆及び建物1棟に、債権額1,000万円とする抵当権設定登記手続の代理業務を受任し、登記原因証明情報(金銭消費貸借契約書等)の作成及び登記申請の代理をした場合の「抵当権設定登記」にかかる金額については以下のようになります。
地区別 課税価格1,000万円の新築建物の抵当権設定登記手続 手数料相場一覧
| |
低額者10%の平均 |
全体の平均値 |
高額者10%の平均 |
| 北海道地区 |
21,785円 |
31,266円 |
45,767円 |
| 東北地区 |
19,091円 |
30,562円 |
47,150円 |
| 関東地区 |
21,961円 |
35,029円 |
54,842円 |
| 中部地区 |
25,783円 |
35,631円 |
56,100円 |
| 近畿地区 |
24,301円 |
40,402円 |
67,429円 |
| 中国地区 |
24,692円 |
35,986円 |
52,208円 |
| 四国地区 |
24,500円 |
35,354円 |
55,250円 |
| 九州地区 |
24,939円 |
34,063円 |
50,175円 |
地区別 課税価格1,000万円の新築建物の抵当権設定登記手続 手数料相場一覧
| 北海道地区 |
| 低額者10%の平均 |
21,785円 |
| 全体の平均値 |
31,266円 |
| 高額者10%の平均 |
45,767円 |
| 東北地区 |
| 低額者10%の平均 |
19,091円 |
| 全体の平均値 |
30,562円 |
| 高額者10%の平均 |
47,150円 |
| 関東地区 |
| 低額者10%の平均 |
21,961円 |
| 全体の平均値 |
35,029円 |
| 高額者10%の平均 |
54,842円 |
| 中部地区 |
| 低額者10%の平均 |
25,783円 |
| 全体の平均値 |
35,631円 |
| 高額者10%の平均 |
56,100円 |
| 近畿地区 |
| 低額者10%の平均 |
24,301円 |
| 全体の平均値 |
40,402円 |
| 高額者10%の平均 |
67,429円 |
| 中国地区 |
| 低額者10%の平均 |
24,692円 |
| 全体の平均値 |
35,986円 |
| 高額者10%の平均 |
52,208円 |
| 四国地区 |
| 低額者10%の平均 |
24,500円 |
| 全体の平均値 |
35,354円 |
| 高額者10%の平均 |
55,250円 |
| 九州地区 |
| 低額者10%の平均 |
24,939円 |
| 全体の平均値 |
34,063円 |
| 高額者10%の平均 |
50,175円 |
建物の保存登記や抵当権設定登記を合わせると、司法書士手数料は、概ね6~7万円程度かかるイメージとなります。
5-5.新築建物不動産取得税
不動産取得税とは、土地や建物などの不動産を取得したときに、その不動産の所在する都道府県が課す都道府県税です。
不動産取得税は、建物が竣工したのち半年以降に都道府県から納税通知書が送付されてきます。
一回のみ支払う税金です。
不動産取得税は、アパートの建築プランによってその税額が大きく変わる税金です。
まず、原則として建物の不動産取得税は、以下の計算式で計算されます。
不動産取得税=課税標準額(固定資産税評価額)×4%
固定資産税評価額については、新築工事費の概ね50~60%程度となります。
さらに、自宅やアパート、賃貸マンション等の住宅については一定の要件を満たすことで、受けられる軽減措置※があります。
※不動産取得日(売買契約書等から総合的に判断して、現実に不動産の所有権を取得したと認められる日)から条例で定められている期限内(30日や60日など都道府県で異なる)に都道府県の税事務所に申告が必要です。軽減措置の内容や申告期限についての詳細は、各都道府県所管の税務署へお問い合わせください。
軽減措置を受けるためには、住宅の面積が以下の要件を満たすことが必要です。
住宅の床面積:50平米以上(戸建以外の貸家住宅にあっては40平米以上)240平米以下
アパートの場合は、一戸当たり40平米以上240平米以下が面積要件となります。
例えば延床面積が300平米あるアパートでも、6戸あれば一戸あたり50平米ですので面積要件に適合します。
面積要件を満たした住宅は、住宅の固定資産税評価額から一戸当たり1,200万円を控除して計算することができます。
不動産取得税で住宅軽減を適用すると、新築アパートの不動産取得税は以下のように減額されます。
不動産取得税=(固定資産税評価額-1,200万円×アパートの戸数)×4%
5-6.融資関連費用
アパートローンを組む際は、通常、銀行に対して事務手数料を支払います。
事務手数料に関しては、5万円や10万円といった金額が一般的です。
事務手数料は銀行によって異なります。
また、銀行によっては保証料を必要とする銀行もあります。
保証料は借入金額や借入年数によって異なります。
保証料としては、例えば貸出期間が20年で、貸出金額100万円あたり15,000円程度の金額が発生する銀行もあります。
アパート経営にかかる費用については、以下の記事もご覧ください。
6.入居者募集費用
アパートが竣工すると、入居者募集費用が発生します。
入居者募集費用については、選択する管理形態によって、発生の仕方が異なります。
6-1.家賃保証型ではない場合
アパートの管理形態には、家賃保証型ではないパターンがあります。
家賃保証型ではないパターンには、「管理委託方式」と「パススルー型サブリース方式」の2つのタイプがあります。
どちらにせよ、入居者募集費用は、一戸当たりの家賃一か月分が目安です。
管理委託方式は、アパートオーナーが管理会社に管理委託する方式です。
管理委託方式では、入居募集は管理会社が行いますが、入居が決まれば管理会社に家賃の1ヶ月分の仲介手数料を支払います。
実質、各戸が決まる度に家賃1ヶ月分の入居者募集費用が発生することになります。
一方で、パススルー型サブリース方式は、管理会社がオーナーからアパートを借り、各住戸を転貸借する管理方式です。
入居が決まると、当該住戸の1ヶ月分の賃料を減額して振り込み、入居者募集費用に代えるパターンが多いです。
実質的には、管理委託方式の入居者募集費用と掛かる費用は同じになります。
6-2.家賃保証型の場合
家賃保証型の管理形式には、家賃保証型サブリースがあります。
家賃保証型サブリースも転貸借ですので、パススルー型サブリースと同様に、アパートオーナーが管理会社とアパート全体の賃貸借契約を1本だけ締結し、各住戸は管理会社が転貸借契約書を締結する形となります。
パススルー型サブリースとの違いは、パススルー型は入居状況に応じて毎月賃料が変動するのに対し、家賃保証型は入居状況に関わらず、原則として毎月賃料は固定となるという点です。
家賃保証型サブリースでは、賃料の免責期間という形でアパートオーナーが入居者募集費用を負担することになります。入居者募集費用は、3~6ヶ月程度と、家賃保証型ではない場合よりも長くなります。
賃料の免責期間については、特に決まりはないので、家賃保証型サブリースを契約する際は、免責期間を短くする交渉を行うことが重要です。
例えば、竣工月が2~3月などの入居者募集に一番良い時期と重なる場合には、入居者がすぐに決まるはずなので、免責期間を2~3ヶ月に短くしてもらう交渉をしてください。
7.アパート建築に必要な自己資金とは
物件を購入するためのローンを組むときに初期費用として、自己資金が必要になります。
金融機関から自己資金を入れるよう求められることもあれば、入れることで審査が通りやすくなるケースもあります。
ただ、現在では自己資金不要で組めるローンもあるため、必ずしも必要なわけではありません。
シミュレーション機能を活用することで、返済計画や収益性を分析できます。
7-1. 自己資金の目安は全体の1~2割
アパート経営を始めるにあたり、1~2割程度の自己資金が必要といわれています。
1~2割といわれる根拠としては、必要となる諸費用が物件価格の1割前後になることが多いからです。
また、金融機関に金利引き下げの交渉をするとき、1~2割の自己資金頭金を入れてほしいと求められるケースがあります。
金融機関から受けられる融資額は、物件価格の7~10割程度だといわれています。
もし、8割の融資額だった場合は、残りの2割分を自身で用意しなければなりません。
7-2. 自己資金以外にかかる費用
自己資金以外にかかる費用として、次のようなものがあります。
- 印紙税や登記依頼にかかる費用
- 険料融資事務手数料
- 不動産仲介手数料(中古アパートの場合)
などの諸費用が必要です。
また不動産取得税は、不動産を取得したとき1度だけ納付しなければなりませんが、取得後約半年後に納税通知書が届くので、忘れないようにしてください。
アパートの自己資金については、次の記事で解説しています。
8.アパート経営の初期費用でローンを組む際の注意点4つ
初期費用を確保するため、金融機関でローンを組むケースは珍しくありません。
ただ、初期費用でローンを組む際には、いくつか注意すべき点があります。詳しく見ていきましょう。
8-1.オーバーローンに注意
オーバーローンとは、物件価格よりも借入金が上回る状態のことで、物件価格と諸費用をともにカバーできます。
アパート経営を始めるにあたり、さまざまな諸費用が発生することは先ほど解説しました。
物件価格の1~2割程度の諸費用が必要だとお話ししましたが、オーバーローンを組めば諸費用分も賄えます。
しかし、オーバーローンは金利が高い傾向があり、月々の返済負担が大きくなりやすいです。月々の返済額が高すぎると、返済困難に陥るおそれは十分あります。事前に収支をきちんとシミュレーションしておくことが大事です。
返済プランを含むアパート経営プランをしっかり検討したい方は「HOME4U(ホームフォーユー)土地活用」を活用すれば、最大10社からプランを入手し比較検討ができます。
アパートを建築した時の予想収益はいくら?
8-2.金利上昇のリスクに注意
金利はさまざまな要因により上昇します。
超低金利が長く続いていますが、これから先もそれが続くとは限りません。今後情勢が変われば、金利が上昇する可能性はあります。
金利が上昇すれば、トータルでの返済額が大きくなるのはもちろん、月々の返済負担も増加してしまいます。
8-3.自己資金なしは審査が厳しい
金融機関により審査基準は異なりますが、自己資金ゼロでは必然的に審査は厳しくなる傾向があります。
自己資金があれば融資額を少なくできるほか、回収できる可能性も高いとみられるため、審査に通りやすくなります。
ただ、審査では契約者の年収や勤務先、現在の借入状況などあらゆる部分を網羅的にチェックされるため、自己資金の有無だけが審査の結果に大きく関わるわけではありません。
8-4.キャッシュフローを意識する
家賃収入を得られていても、月々の返済額が多すぎると経営が行き詰まるおそれがあります。
キャッシュフローを意識し、毎月手元にどれくらいのお金が残るかを考えながら経営を行わなければなりません。
返済比率は40%以下に抑えることが基本といわれています。返済比率とは、トータルの家賃収入を返済額で割った数字です。
詳しくは、次の記事もご確認ください。
9.アパート経営で成功するための建築会社の選び方
アパートの初期費用は自分で計算するには限界があり、設計を進めていくことで金額を把握できるようになっていきます。そこで、プロの出番です!
複数の建築会社に見積もりを出してもらい、妥当な初期費用の相場感を見ながら、最も信頼できる建築会社を選んでください。
初期費用を概算するうえでおすすめなのが、「HOME4U(ホームフォーユー)土地活用」を利用したプラン一括請求です。複数の建築会社に、初期費用や収益計画を盛り込んだ活用プランをまとめてプラン請求できます。
全国の一流のハウスメーカーと多数提携している「HOME4U」なら、あなたの土地の特性を最大限に活かしたアパートの建築プランを提案してくれます。
提案書の中には、初期費用の内訳もしっかりと書かれているので、初期費用がいくらくらいするのかがすぐに分かります。複数の提案書を見比べることは、適正な初期費用も選ぶことにもなりますので、検討の際はぜひ「HOME4U 土地活用」をご利用ください。
この記事のポイント まとめ
アパートの建築を計画するうえで必要な初期費用は?
アパートの請負契約と着工に必要な初期費用は?
アパートの工事中に発生する初期費用は?
アパート竣工事に発生する初期費用は?
- 火災・地震保険料
- 登記関連費用
- 新築建物登録免許税
- 抵当権設定登録免許税
- 司法書士手数料
- 新築建物不動産取得税
- 融資関連費用
詳細は「アパート竣工時に必要な費用6つ」をご一読ください。
アパート経営の収益・節税プランを企業に請求できます!
あなたに合った活用法が分かる!
【全国対応】HOME4U「土地活用」
この記事の執筆者
竹内 英二
不動産鑑定士事務所および宅地建物取引業者である(株)グロープロフィットの代表取締役を務める。不動産鑑定士、宅地建物取引士、賃貸不動産経営管理士、不動産コンサルティングマスター(相続対策専門士)、中小企業診断士。
(株)グロープロフィット
理想のアパート建築を実現させるには、構造/工法/間取りなどの設計部分はもちろん、 建築費や収支計画をまとめた建築プランを複数の企業に依頼し、各社の提案を比較して、 長期安定アパート経営につながる「収益最大化」プランを見つけることが大切です!
ただ、アパート建築の依頼先は「ハウスメーカー」や「建築会社」「専門会社」など様々です。 「どこに依頼すればいいか分からない」「何から始めたらいいか分からない」とお悩みでしたら、 複数の信頼できる企業へまとめて相談、プランが請求できる「HOME4U 土地活用」をご利用ください。
“HOME4U 土地活用 3つの特徴”
- 提携企業は、信頼できる業界大手企業が勢ぞろい!この顔ぶれはHOME4Uならではのラインアップ!
- 複数社へプラン一括請求、比較できるからいろんな工法や間取り、坪単価の提案を幅広く受けることができる!
- NTTデータのグループ企業「NTTデータ・ウィズ」が運営。19年の実績があり、セキュリティも安心!
アパートを建てたい土地の住所など簡単な項目を入力するだけで、厳しい審査によって厳選された複数の大手企業へまとめてプラン請求ができるので、各社の提案を比べながら、あなたの土地にぴったりなアパート建築プランを見つけることができます。
ぜひ「HOME4U 土地活用」を利用して、あなたの土地・地域、希望にあったアパート建築の「収益最大化」プランに出会ってください!
ぜひコチラから大手企業に一括相談して、成功への足掛かりをつかんでください!



![[19周年]利用者数1,000万人[HOME4U年間利用者数2020年5月現在]](/img/common/header_f1.jpg)