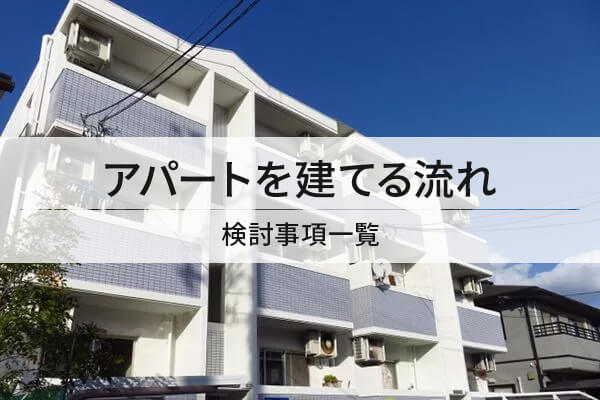アパートの建て替えで、目安となる要素は以下の5つです。
- 築年数
- 収益状況
- 高額なリフォーム費用が必要になる場合
- 空室率が5割以上
- 入居者のニーズ変化
このような要素が見られるときには、建て替えをすることで、大まかに以下のようなメリットが得られます。
この記事では建て替えで必要な、アパートの建築費用をシミュレーションすることもできるので、併せて確認してみてください。
また、以下のボタンから土地情報を入力すると、最大10社の大手ハウスメーカー・建築会社から建築費や予想収益が含まれた、「アパート建て替えプラン」を取り寄せることができます。
「収益を改善したい」「いくらで建て替えられるのか知りたい」という方はぜひご活用ください。
1. アパートの建て替え時期を判断する5つの目安
アパートの建て替えを判断する目安は、大きく分けて以下の5つです。
- 築年数
- 収益状況
- 高額なリフォーム費用が必要になる場合
- 空室率が5割以上
- 入居者のニーズ変化
1-1.築年数

アパートの耐用年数の目安は、構造別に次のようになっています。
アパート構造別 耐用年数一覧
| 木造 |
50~60年 |
| 鉄筋造 |
55~75年 |
| 鉄筋コンクリート造 |
100年~ |
しかし、建て替えのおおよその検討時期は30~40年です。
アパートは、大体15~20年で大規模な修繕を必要とする箇所が生まれてきます。特に木造アパートの場合は、構造上リノベーションがむずかしく、耐震性の問題も関わってきます。
その場合、建て替えを検討する要素として、以下のような点に考慮してみてください。
容積率に余裕があれば現状よりも戸数の多いアパートに建て替えることができ、部屋数が増加すれば家賃収入も増えます。
逆に建築基準法の改正などによって、建て替えた場合に現状よりも小さいアパートしか建てられないようなケースは、リノベーションのほうが戸数を減らさずにすむので有利になります。
オーナーの子どもにアパート経営を引き継ぐ意思がある場合は、さらに長期間の利用を目的として、新しく建て直したほうがよいでしょう。後継者にアパート経営を引き継ぐことで節税効果もあります。
アパートと敷地を売却して現金化すると、高額の相続税がかかってしまいますが、アパート経営を相続してもらえれば評価額を引き下げることができるので節税になります。
ただし、入居者が減っておらず、安全面でも問題がない状態であれば、無理に建て替える必要はありませんので、アパートの状況に応じて、判断してみてください。
アパートの建て替えは、築30年を超えた頃から検討するオーナーが増えます。建物の耐用年数は50年以上はありますが、減価償却のメリットが享受できなくなるころから、検討してもいいでしょう。建物減価償却は構造によりますが、22年(木造)~47年(RC造)、メーカー系で多い軽量鉄骨造は27年で償却されます。また、借り入れ年数もこれと同じ期間程度(30年程度)で設定することが多いため、30年を超えると残債がなくなり(あるいは少なくなり)、建て替えが検討しやすくなります。建て替えの際には、立ち退きに時間がかかったり、新たな建物プランの検討など、想定以上に時間がかかる例も多いため、検討する場合は早め早めの対応がいいでしょう

不動産エコノミスト・吉崎誠二
1-2.収益状況
空室が増え、入居者が集まらなくなってきたら、建て替えの時期かもしれません。また、金銭面の見地に立って考えるならば、建て替えを検討するために気に留めておくべきことがあります。
・低金利であること
アパートの建て替えには高額な費用がかかるため、ほとんどの場合は銀行などの金融機関から融資を受けることになります。
日本はずっと超低金利が続いていますので、このような時に思い切って建て替えをすればローン返済の負担を軽減することができます。
とはいえ、選択肢は建て替えだけでなく、リフォーム・リノベーションや、家賃改定なども検討されますので、市場調査を実施し、プロにも相談して、これからの方針を決めてください。
アパートの建築費や将来の収益はいくら?
大手10社のプラン比較はコチラから!
1-3.高額なリフォーム費用が発生する場合
高額なリフォーム費用が立て続けに発生するような場合には、建て替えを検討すべきです。
かけようとしているリフォーム費用が高額であるか否かについては、投資に対するリターンで判断する方法があります。
例えば、あるアパートの現在の月額の家賃が5万円であるとし、60万円のリフォーム費用を投じたことで賃料が上がって、月額5.5万円の家賃になったと考えます。5千円の賃料アップを年間に直すと、6万円の上昇となり、60万円の投資に対して年間6万円のアップですから、表面利回りとしては10%の投資となります。すると投資額の回収にかかる期間は10年です。
築年数の古い物件で、回収に10年もかかる追加投資を行ってしまうと、その間に他の修繕で別の追加投資が雪だるま式に発生することが予想されます。
このような場合には、建て替えた方が収益性を望めるでしょう。
躯体の状態や費用面を考慮したうえで、どちらの方がメリットが大きいかを考えて検討してみてください。
建て替えで発生するアパートの建築費用はこちらでシミュレーションできます。
1-4.空室率が五割以上
建て替えには、今入居している方々に対しての立ち退き交渉が必須となります。
アパート経営は、借入金が多いと空室率が3~4割程度でも苦しくなりますが、その段階で立ち退きに手を付けてしまうと、相手が多いため立ち退き料も多くかかり、交渉も難航する可能性があります。
よって、立ち退きに着手するのは、空室率が5割以上に増えてからが望ましいです。さらに言えば、8割くらいになった段階で本格的に動き始めるほうが無駄はありません。
入居者が自然に減っていき、良い段階に来たところで立ち退きを開始して、本格的に建て替えを進めて行くことをおススメします。
1-5.入居者のニーズ変化
入居者のニーズ変化は、主に以下のような点で起こります。
- 建物デザインや設備が時代遅れ
- 周辺に新しいアパートが出来た
アパートが建ってから年数が経ってくると、デザインや設備が古くなります。例えば、バスとトイレ、洗面が一体型となっている3点ユニットや、和室のある部屋等は入居者募集のボトルネックとなり、空室増加の原因になります。
一方、現在は3畳ほどの狭いワンルームでもロフトを装備した部屋が人気になって来て、若い人を中心に多少家賃が高くてもロフトのあるなしで入居を決めるようになってきました。
また、新規入居者は新しいアパートを好みますので、近辺に新しくアパートが出来た場合には、古いアパートは家賃を下げざるを得なくなります。
アパート建て替えについて検討中の方は「HOME4U 土地活用」を使えば、エリアのニーズに合った建て替えプランを最大10社のハウスメーカーから取り寄せることができます。
アパート建築のプランを請求する(無料)
2. アパート建て替えのメリット・デメリット
2-1.アパートを建て替えるメリット
アパートを建て替えることによって生まれるメリットを2つご紹介します。
2-1-1.減価償却費によってキャッシュフローが良くなる
減価償却費とは、時間の経過によって価値が薄まる固定資産に対し、取得にかかった費用の全額を耐用年数に応じて各会計期間に分割、配分する費用のことを言います。
この減価償却費が発生する期間である法定耐用年数は、建物の構造によって以下のように決まっています。
構造別 耐用年数一覧
| 木造 |
22年 |
| 厚みが3mm超4mm以下の鉄骨造 |
27年 |
木造アパートなら、22年間にわたり建物の取得原価が費用として配分され、建物の簿価(確定申告をする上で、帳簿に載る資産価格のこと)はその分だけ下がります。減価償却費と建物簿価の関係は以下の通りです。
築年数と減価償却費・建物簿価の関係 一覧表
| 築年数 |
減価償却費 |
建物簿価 |
| 竣工年 |
0円 |
2,200万円 |
| 1年目 |
約100万円 |
2,100万円 |
| 2年目 |
約100万円 |
2,000万円 |
| ~中略~ |
| 21年目 |
約100万円 |
100万円 |
| 22年目 |
約100万円 |
1円 |
| 23年目 |
0円 |
1円 |
建物は減価償却され、耐用年数満了時には最終的に備忘価格の1円まで償却されます。それ以降、減価償却費は発生しません。
減価償却費が発生しなくなるとその分利益が増えますが、税金も増えてしまいます。
すると、耐用年数を満了したアパートは、家賃が低くなっているにもかかわらず税金が増えてしまうため、最終的なキャッシュフローが悪化します。
この仕組みによって、アパート経営では、耐用年数満了後の物件はキャッシュフローが悪くなります。元に戻すには、建て替えを行って、再度、毎年減価償却費が計上できるような状況にすることが必要です。
2-1-2.支出の削減
築年数が古い物件は、収入が減るばかりか支出も多くなります。
そしてその支出は「建て替え」によって減らす事ができます。
増額する費用は主に以下の3つです。
- 修繕費(大規模修繕費を含む)
- 空室対策のためのリフォーム
- 入居者募集費用
築年数が古くなると、各部屋の細かい修繕の他、外壁塗装、給湯器の入替等の大規模修繕費も増えていきます。
更に時代と共に仕様とニーズがマッチしなくなると、お金のかかる大規模なリフォームが必要となります。
また、古い仕様が不満となり、空室が増えれば、不動産会社へ支払う仲介手数料などの入居者募集費用が発生します。
これらの費用は、「建て替え」をする事で抑えていく事ができます。
2-2.アパートを建て替えるデメリット
アパートを建て替えることのデメリットは、大きく分けて以下の2つです。
2-2-1.立ち退き交渉が必要
アパートを建て替えるには、今現在入居している方々全員に対して、立ち退きを要求し、同意を得なければなりません。
借地借家法により、立ち退きを行うには、正当事由とよばれる理由と、財産上の給付(立ち退き料のこと)を申し出ることが定められています。交渉は難航することも多く、立ち退き料は人数が多いほど、その分負担しなければならない金額も増えてきます。
立ち退き料に関する規定はありませんが、普通借家契約に基づく賃借人への支払いは、概ね家賃の6+α カ月程度+引っ越し費用、というのが相場のようです。また、立ち退き交渉は6カ月以上前から行うことが基本です。ただし、規定がないわけですから、納得されない入居者もおり、そのさいには弁護士などに依頼します。そうなれば、立ち退き期間は長くなります。定期借家契約の場合は、立ち退き料は原則的には払いませんが、多少考慮するとスムーズに進むと思われます。

不動産エコノミスト・吉崎誠二
2-2-2.多額の費用がかかる
建て替えには、解体費用、退去費用に加え、新しい建物を立てるための新築費用もかかります。結果としてリフォームなどの方法と比べ、多額の費用が必要となります。
実際どのくらいの費用がかかるかについては、以下の記事でおおまかにシミュレーションをして頂けます。
おすすめの建築会社・メーカーについては以下の記事をご覧ください。
3. アパートを建て替えで押さえておきたいポイント
3-1.土地のニーズを意識する
新築ではなく建て替えであっても、周辺調査を行いどのようなニーズがあるかを把握しておくことが必須です。
アパート経営を始めた当時と比較し、数十年がたてば周辺の環境も変わります。住民構成や周辺の商業施設や交通機関、公的機関が変わってくるとアパートのニーズは変わります。さらに、競合となる賃貸物件も変化しているでしょう。
それらの変化をもとに、その地域ではどのような賃貸物件が求められているのか、それは今後数十年でどのように変化するかを調査します。ターゲットを明確にしてニーズのある建物を作ることが最も大きな空室対策となり、建て替えを成功させる要因となります。
3-2. 解体費用・新築費用を知っておく
建て替えにかかる費用は立ち退き費用のほか、解体費用・新築費用が多くを占めます。
躯体ごとのアパートの解体費用の相場は以下の通りです。
|
アパートの躯体別 解体費用一覧
|
|
木造
|
坪4~5万円
|
|
鉄骨造
|
坪6~7万円
|
例えば80坪の木造アパートであれば、320万円~400万円程度かかることになります。詳しくは以下の記事でご確認ください。
アパートの新築費用は以下の坪単価をもとに計算ができます。
|
アパート構造別 建築費坪単価一覧表
|
|
木造
|
坪80万円前後
|
|
軽量鉄骨造
|
坪75万円前後
|
|
重量鉄骨造
|
坪90万円前後
|
アパートの建て替え費用やアパートの建築費については、以下の動画・関連記事をご覧下さい。
また、以下のボタンから土地の情報を入力すると、あなたの土地にあったアパートの建築費の見積もりを、最大10社の建築会社から無料で取り寄せることができます。
3-3.立ち退き交渉は計画的に行う
建て替えの際に、計画的に行わなくてはならないのが立ち退き交渉です。スムーズに進めるには、空室率が8割程度になってから、6か月以上の期間をとって交渉にあたるのが成功のコツです。
最も注意したいのは、裁判にならないように進めること。借地借家法では賃貸人(大家側)の立場はどうしても弱くなります。できる限り交渉で解決するのがベストです。立ち退きについては以下の記事もご確認ください。
3-4.相続税対策を意識する
老朽化で空室が増えてくると、相続税評価額が下がらなくなります。
賃貸物件の相続税評価額は、建物に関しては借家権割合による評価減、土地に関しては貸家建付地による評価減の適用を受けます。
借家権割合とは、他人に賃貸している建物を評価する際に用いる減価率で、全国どこでも一律30%と決められている減価の割合です。
一方他人に賃貸する建物が建っている土地のことを貸家建付地といい、権利が制約されているため、一定のルールで減価されます。
相続税評価額が下がると、資産の額が減るため、相続税が節税されます。
賃貸部分の土地と建物の相続税評価額の算式は、満室の場合には以下の通りです。
賃貸部分 土地と建物の相続税評価額計算式(満室の場合)
| 建物 |
貸家の建物評価額=建物固定資産税評価額×(1-借家権割合) |
| 土地 |
貸家建付地=路線価評価額×(1-借地権割合×借家権割合) |
借地権割合は30%~90%の範囲でエリアによって指定されています。
60%だった場合、土地は路線価から18%(=30%×60%)減額された数値が相続税評価額となります。
アパートが満室であれば、建物は固定資産税評価額から30%減額された数値が相続税評価額となります。
満室ではない場合の計算式は、正確には以下のようになります。
賃貸部分 土地と建物の相続税評価額計算式(満室ではない場合)
| 建物 |
貸家の建物評価額=建物固定資産税評価額 ×(1-借家権割合×賃貸割合) |
| 土地 |
貸家建付地=路線価評価額 ×(1-借地権割合 × 借家権割合 × 賃貸割合) |
ここで表される賃貸割合は以下の式で計算されます。
(課税時期において賃貸されている各独立部分の床面積の合計)÷(その貸家の各独立部分の床面積の合計)
より簡単な言い方に直すならば、「入居率(=1-空室率)」ということです。
以下のような条件のアパートを例として考えてみましょう。
入居率別 相続税評価額の事例
| 建物の固定資産税評価額 |
2,000万円 |
| 路線価評価額 |
3,000万円 |
| 借地権割合 |
60% |
このアパートが満室の場合、賃貸割合は100%となるため、相続税評価額は以下の通りとなります。
建物
貸家の建物評価額=建物固定資産税評価額 ×(1-借家権割合×賃貸割合)
=2,000万円 ×(1-30%×100%)
=1,400万円
土地
貸家建付地=路線価評価額 ×(1-借地権割合×借家権割合×賃貸割合)
=3,000万円 ×(1-60%×30%×100%)
=2,460万円
相続税評価額
建物+土地=1,400万円+2,460万円
=3,860万円
一方で、空室率が80%、つまり賃貸割合が20%となってしまったアパートの評価額を計算してみます。
建物
貸家の建物評価額=建物固定資産税評価額 ×(1-借家権割合×賃貸割合)
=2,000万円 ×(1-30% × 20%)
=1,880万円
土地
貸家建付地=路線価評価額 ×(1-借地権割合 × 借家権割合 × 賃貸割合)
=3,000万円 ×(1-60% × 30% × 20%)
=2,892万円
相続税評価額
建物 + 土地=1,880万円 + 2,892万円
=4,772万円
満室時と比較すると、912万円評価が上がっていることが分かります。
評価が上がるということは、相続税が上がることを意味します。
アパートの空室が発生することで、土地の評価額まで連動して上がってしまうこともポイントです。
ただし、相続時においてたまたま空室だった部分が、全て空室として扱われてしまうわけではありません。
一時的な空室の場合、空室扱いではなく「賃貸部分」とされることが認められており、そうなるかどうかは、以下のような条件を総合的に勘案した上で判断されます。
・空き室であっても「賃貸部分」と認められる条件
- 各独立部分が課税時期前に継続的に賃貸されていること
- 賃借人の退去後速やかに新たな賃借人の募集が行われていること
- 空室の期間、他の用途に供されていないこと
- 空室の期間が課税時期の前後の例えば1ヶ月程度であるなど一時的な期間であること
- 課税時期後の賃貸が一時的なものではないこと
なお、建て替えを必要とするような物件は、「4.」の条件によって、一時的な空室扱いとはならない部屋が多くなります。
最終的な評価額を決める場合には、税務署に相談することが必要です。
相続税対策としてアパート建て替えについてご検討中の方は「HOME4U 土地活用」をご活用ください。最大10社のハウスメーカーから相続税対策を施した経営プランを手に入れられます。
土地に建物をたてた際の節税額はいくら?
3-5.借入金を残す
相続対策として、借入金を使ってアパートの建て替えを行い、「わざと借入金を残す」ということが相続税を減らす効果を生みます。
例えば、借入金4,000万円を使って建て替えた場合の相続税評価額を計算してみましょう。建物の固定資産税評価額は新築請負工事費の50%程度となるため、2,000万円とします。
アパート建て替え時 相続税評価額 事例
| 借入金 |
4,000万円 |
| 建物の固定資産税評価額 |
2,000万円 |
| 路線価評価額 |
3,000万円 |
| 借地権割合 |
60% |
| 空室の状態 |
満室 |
満室時の相続税評価額は、前節の計算例と同じですので3,860万円となります。借入金のマイナスを考慮すると、相続税評価額は以下のようになります。
相続税評価額=土地建物評価額-借入金
=3,860万円-4,000万円
=▲140万円
上記の例では、借入金を新たに使うことによって、アパートの建て替えを行うことで相続税評価額を大きく下げられます。
借入金を完済し、空室の多いアパートは、相続税評価額が高くなってしまうため新築アパートと比べると相続税対策効果が薄まります。相続対策としてアパート経営を行うなら、建て替えを行って相続対策効果を回復させることをおススメします。
4.アパートを建て替えた方がいいかどうかから相談できる施工会社の選び方
選ぶ際の基準は以下の通りです。
- 初めての人をサポートした実績がある。
- 経験豊富な会社である。
- 建て替えるべきかどうかの選択肢を与えてくれる。
- 度重なる相談に親身に対応してくれる人がいる。
様々の条件下でアパートを建築した実績を持つ会社であれば、今まで建て替えに踏み切ったアパートがどういう状態であったか、今検討中のアパートと比べてどうなのかなど、事例を比較検討できます。
初心者の目線にあわせて、建て替えるべきかどうかの選択肢と判断材料を与えてくれ、親身に対応してくれる会社であれば、適切な判断が下しやすいでしょう。
「HOME4U(ホームフォーユー)土地活用」ではお客様の状況に合わせて、「上記の基準を満たしたアパート建て替えの不安点について知見・経験が豊富な企業」を選んでご紹介いたします。
アパート経営の収益・節税プランを企業に請求できます!
あなたに合った活用法が分かる!
【全国対応】HOME4U「土地活用」
この記事の執筆者
竹内 英二
不動産鑑定士事務所および宅地建物取引業者である(株)グロープロフィットの代表取締役を務める。不動産鑑定士、宅地建物取引士、賃貸不動産経営管理士、不動産コンサルティングマスター(相続対策専門士)、中小企業診断士。
(株)グロープロフィット
土地活用の相談先を探すなら一度の入力で複数の大手企業へ一括プラン請求!
土地活用の相談先は「建築会社」「ハウスメーカー」「専門業者」など色々あって、どこに相談したら良いか、迷うものです。
それに、あなたの土地にはどんな活用法が向いているのかも、自分ではなかなかわからないですよね。わからないからといって、もしも一社にしか相談しなかったら…
- 他社ではもっと高収益なプランがあるかもしれないのに、見落としてしまうかもしれません
- その土地に適していないプランで活用を始めてしまうリスクがあり、後になって失敗してしまう可能性があります
つまり失敗しないためには、できるだけ多くの相談先を見つけ、たくさんのプランを比較してから決めることがとても重要です!
「HOME4U土地活用」なら、土地活用したいエリアなど簡単な項目を入力するだけで、複数の大手企業へまとめてプラン請求ができるので、各社の提案を比べながら、収益を最大化するためのプランを見つけることができます。
しかも「HOME4U土地活用」は
- 信頼できる業界大手企業が勢ぞろい!この顔ぶれはHOME4Uならではのラインアップ!
- NTTデータグループの「NTTデータ・ウィズ」が運営。19年の実績があるので、安心してご利用頂けます
ぜひコチラから大手企業に一括相談して、成功への足掛かりをつかんでください!
カンタン60秒入力 土地の情報を入力するだけ!



![[19周年]利用者数1,000万人[HOME4U年間利用者数2020年5月現在]](/img/common/header_f1.jpg)