この記事の執筆者
この記事の執筆者
木﨑 海洋
所属 行政書士きざき法務オフィス 代表
きざきFPオフィス(株)代表取締役
職業 行政書士、宅地建物取引士、賃貸不動産経営管理士、ファイナンシャルプランナー(AFP)ほか
相続専門の行政書士と不動産・FP業務を行う。
同時に「こころ亭久茶」として「落語で学ぶ相続と不動産」などセミナー講師をする。
落語形式の講演は珍しく、難しい話を笑いながら学習できると評判となり全国で年間140回の講演をする。
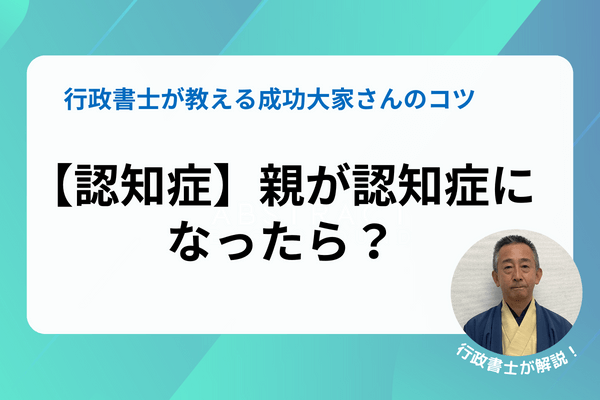
A氏 : えっ!? 売れないんですか?
木崎 : はい
A氏 : 母も同意しているのに?
木崎 : 土地所有者であるお父様は重い認知症です。
お父様の土地売却の意思が確認できないので売ることはできないんです。
A氏 : 困ったな~
不動産売買や活用(建替え、賃貸、リフォームなど)をする際、このような会話がよくあるそうです。
今回は行政書士きざき法務オフィス代表で、相続・不動産取引などを専門とする木崎 海洋先生(※崎はたつざき)に“親が認知症になった場合”をテーマにお話を伺いました。
不動産売買や活用は「法律行為」となり、不動産所有者本人の「意思能力」が必要です。意思能力とはその行為の結果「売却したら不動産の所有権を失う」ということを理解することです。
意思能力がない場合の法律行為は無効となり、いくら配偶者や子供が同意をしても有効にはなりません。不動産所有者本人の意思が確認できない以上、このままでは売買や活用はできません。ここでは、意思能力のない方の症状を「認知症」と表記します。

では、昔からこうだったのでしょうか?(昔とは、20~30年以前を想定してください)民法の規定は昔も今も変わりません。しかし、実務現場ではちょっと違っていました。
昔は不動産所有者が認知症で意思能力がない場合でも、配偶者や子供が同意しておりかつ本人のため(例:父の入院治療費にあてるため)であれば不動産会社も「お父さんのためで家族全員が同意をしているなら…」と売却に協力をしてくれていたこともあったようです(本来はダメですよ)。
また、不動産の登記をする司法書士さんも「実印、印鑑証明、登記済み権利証」があれば登記ができたので、本人の意思確認を厳格にしなくても登記をしてくれたこともかつてはあったようです。「よかれ」と思い協力してくれた不動産売買。それで特に問題が起きることは少なかったのです。
しかし今は違います。本人の意思を確認せず、不動産売買や活用をすると後にトラブルとなる可能性があります。
例えば長男が認知症の父の不動産を売却したとしましょう。すると次男や長女から「認知症の父の土地を兄が勝手に売った」と争いになります。
勝手に売却した長男も責任追及されますが、お父様の意思確認をせず仲介した不動産会社の落ち度も追求され損害賠償を請求される可能性もあります。不動産会社はトラブルを避けたいので、認知症で意思の確認ができない取引きはしたくないのです。
司法書士さんの登記手続きも厳格になりました。特に不動産の売主の「本人確認」や「意思確認」を怠り登記をしてしまったら大きなペナルティを課されます。
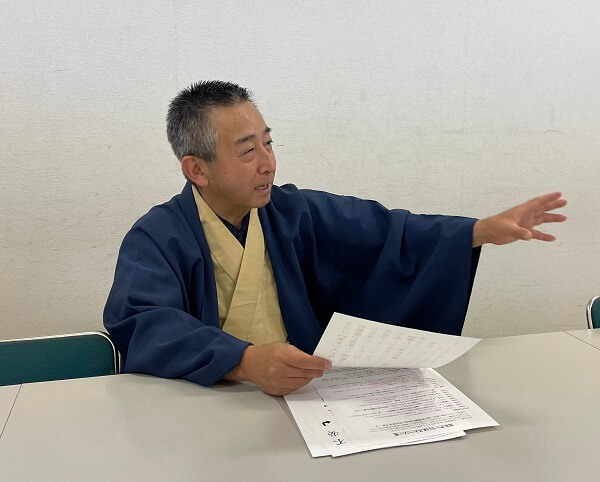
では、どうして厳格化されたのでしょうか?ひとつは、コンプライアンス(法令遵守)が重視され、違反は容赦なく批判される時代になったということ。そして、不動産取引きや相続に関する争いが増えてきたことも要因です。
最近は、兄弟姉妹の信頼関係が希薄になっているなと感じる場合も増えました。加えて今はインターネットで容易に情報を入手できる時代です。専門家に相談しなくても兄の行為が不正だということを知ることができ、争いに発展しやすいという側面もあります。
「不動産会社が売ってくれない」「建築業者が建ててくれない」「司法書士が登記をしてくれない」では何もできないですね。では、どうしたらいいのでしょうか? 対策はあります。
「老朽化が進んでおり近々建替えをしなければいけない」
「使っていない土地をいずれは売却する予定だ」
こういったニーズが少しでもあるなら、認知症になる前に考えましょう。建替えは古家解体や境界確定なども要し完成まで時に数年かかります。その途中で認知症となったら計画や工事が中断されることもあります。早めの計画が必要です。
土地を売りに出してもすぐに買主が見つからない場合もあります。そんなときは、先に子供の名義に移転しておくことも対策のひとつです。
このような対策が理想ですが、もし間にあわなかったらどうなるでしょうか。
「成年後見制度」を利用すれば後見人が不動産売買や活用(制約もあり)をすることもできます。しかし、後見人は何でも代わりにできるわけではありません。
例えば「居住用不動産の売却」をするには家庭裁判所の許可が必要です。つまり住むところ(自宅)は、生活する上でとても大切。そのため後見人といえども容易に売却ができないのです。
「自宅を売却しなければ生活費が足りない」など売却の必要性がない限り許可を出してくれません。

成年後見制度の利用には手間と時間、そして費用がかかります。医師の診断書など多くの書類を揃え家庭裁判所へ申し立てをします。そこから審理や登記を経て後見人がつくまで1年以上かかる場合があります。
配偶者や子供が後見人に選任された場合は通常報酬は発生しません。しかし、家庭裁判所は家族が後見人として不適格と判断した場合、弁護士や司法書士など第三者を後見人に選任します。家族以外が後見人に選任された場合、後見人の報酬として毎月2万円~6万円程度を本人(成年被後見人)が亡くなるまで支払わなければなりません。
成年後見制度は有効な制度ではあるものの、使いづらい一面もあります。そこで現在、利用しやすくなるよう法改正の議論がされています。
民事(家族)信託という言葉を聞いたことがあるでしょうか。
信託銀行等を利用するものを「商事信託」、信託銀行等を利用せず家族だけで完結するものを一般的に「民事(家族)信託」と呼びます。
制度の詳細は割愛するとしまして、今回の親の認知症に対する不動産について解説します。
例えば、「いずれ土地を売却する」「数年後に家を建替えする」といったケース。いざその時になってお父様が認知症になっていては希望通り進まないので、お父様が元気なうちに父と子供の間で「信託契約」を締結しておきます。信託契約で子供に売却や建替えの権限を与えておけば、父が認知症になっても売却や建替えをすることができます。
成年後見制度と似ていますが、成年後見制度より任せる範囲が広く制約も少ない(家庭裁判所の管理下ではない)と思っておけばいいでしょう。信託契約は親子でできますが、内容の構成や契約書作成には専門知識が必要です。信託専用口座の開設や不動産の「信託登記」も伴いますので、専門家に相談をしてみましょう。
「ウチのオヤジの時はできたのに…」ということが今はできなくなりました。
ムリにやろうとすると後に大きなトラブルになります。昔と今とでは違う、ということを知っておいてください。
しかし、対策はあります。専門家に相談してみましょう。何らかの対策が見えてくるはずです。
この記事の執筆者
この記事の執筆者
木﨑 海洋
所属 行政書士きざき法務オフィス 代表
きざきFPオフィス(株)代表取締役
職業 行政書士、宅地建物取引士、賃貸不動産経営管理士、ファイナンシャルプランナー(AFP)ほか
相続専門の行政書士と不動産・FP業務を行う。
同時に「こころ亭久茶」として「落語で学ぶ相続と不動産」などセミナー講師をする。
落語形式の講演は珍しく、難しい話を笑いながら学習できると評判となり全国で年間140回の講演をする。
お役立ちガイド内検索
HOME4Uでは、さまざまな形でアライアンスを組むパートナーサイトさまを募集しています。お問い合わせフォームよりお気軽にお問い合わせください。
使い方に関するご不明点など、お困りのことがありましたら専属のオペレーターがお受けします。何でもお気軽にご相談ください。
電話
0120-245-171
受付時間
平日10:00~18:00
土地活用に関して
土地活用の方法
土地活用の相談先
空き家の活用方法
駐車場経営
アパート経営・マンション経営に関して
アパート経営の基礎
アパートの建築費
アパート経営の利回り
アパート経営の収入
アパートの建て替え
アパートローンについて
マンション経営の基礎
マンションの建築費
マンション経営の利回り
マンション経営の収入
賃貸経営に関して
賃貸併用住宅経営の基礎
戸建て賃貸経営の基礎
ビル経営の基礎
店舗付き住宅の基礎
土地活用、不動産投資の収益最大化プランを見つけるなら、「HOME4U(ホームフォーユー)土地活用」で!
NTTデータ・ウィズが運営する「HOME4U土地活用」は、全国の大手企業から、最大10社にまとめて無料で土地活用・不動産投資の一括プラン請求ができるサイトです。マンション経営やアパート経営、駐車場経営、賃貸併用住宅、大規模施設などの収益性の高い土地活用や不動産投資を検討している方は、ぜひご利用ください。プランを比較することであなたに合った収益最大化プランを見つけることができます。土地活用、不動産投資の無料一括プラン請求なら、「HOME4U土地活用」にお任せください。
電話でもプラン請求をお受けします。「個人情報の取り扱いについて」に同意の上、お電話ください。