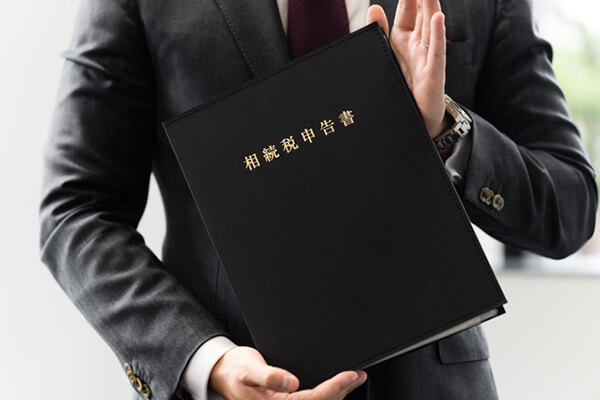
平成25年度税制改正で平成27年(2015年)1月1日以後の相続等の基礎控除額が引き下げられ、相続税の申告が必要な人が増えています。
死亡者数に対する相続税の課税件数の割合を見てみると、基礎控除額の引き下げ前の平成26年(2014年)の4.4%に対し、平成27年(2015年)分が8.0%、平成28年(2016年)分8.1%、平成29年(2017年)分8.3%となっており、実際に増えていることがわかります。
亡くなった方100人中、相続税の申告が必要な人は8人くらいということになります。このデータからは、思ったより少ないと感じる方も少なくないかもしれませんが、もしかするとご自身がその8人に該当するかもしれません。
いざという時に慌てないために、事前に正しい計算方法を理解しておき、相続する・相続させる立場それぞれで相続税が発生するかどうかを知っておくことが大切です。
今回は、少し難しい相続税の仕組みとその計算方法についてわかりやすく説明していきます。
1. 相続税の基礎知識
ある方が亡くなった場合、その方を被相続人といい、相続や遺贈によって被相続人の財産を取得する人を相続人といいます。
被相続人の財産が相続税の基礎控除額を超える場合、相続人が相続税を納めることになります。
1-1. 相続税のかからない範囲
相続人が相続や遺贈で被相続人から取得する相続財産には、プラスの財産とマイナスの財産があります。
プラスの財産とは、例えば現預金や有価証券、土地や建物などの不動産、自動車や貴金属などの動産、その他電話加入権やゴルフ会員権などが該当します。
また墓地などや仏壇などは、財産の性質上非課税とされていて相続税はかかりません。
マイナスの財産は被相続人の債務で、例えば借入金や未払の税金関係などが該当します。
被相続人が生前に購入していた墓などの非課税財産にかかる未払金は債務にはなりません。
その他にも、被相続人の債務ではありませんが、葬儀費用も、相続税の計算上差し引くことができます。
ちなみに、プラスの財産よりマイナスの財産が上回るときには相続放棄や限定承認という手続きをとることができます。
相続放棄や限定承認は、相続があったことを知った日から3ヵ月以内に家庭裁判所に申し立てる必要があるのでご注意下さい。
ここまでをまとめると、
といえます。
この相続税のかかる財産が、相続税の基礎控除額以下であれば相続税はかかりません。
では相続税の基礎控除額はいくらかというと、
になります。
例えば法定相続人が妻、長男、長女の3人であれば、
が基礎控除額となります。
コラム ~法定相続人とは?~
法定相続人は、民法で定められています。
被相続人の配偶者は常に相続人になり、配偶者以外の人は、次の順序で配偶者とともに相続人となります。
【第1順位】 被相続人の子供
被相続人の子供が既に亡くなっている場合は、その子供の子供や孫などの直系卑属が相続人となります。
子供も孫もいる場合は、被相続人により近い世代である子供が優先されます。
【第2順位】 被相続人の父母や祖父母などの直系尊属
父母も祖父母もご存命の場合、被相続人により近い世代である父母が優先されます。
第2順位の人は、第1順位の人がいないときに相続人になります。
【第3順位】 被相続人の兄弟姉妹
第3順位の人は第1順位、第2順位の人もいないときに相続人となります。
例えば、被相続人の兄弟姉妹が既に亡くなっている場合、その亡くなった兄弟姉妹の子どもが相続人となります。
注意すべき点もいくつかあります。
相続を放棄した人は初めから相続人でなかったものとされます。また、内縁関係の人は相続人に含まれません。
法定相続人の数は、相続を放棄した人も人数に含みます。
また、養子がいる場合には、実際の養子の人数にかかわらず、実子がいる場合は養子のうち1人まで、実子がいない場合には2人までとします。
例えば、妻と子(第1順位)が2人いて、孫2人を養子にしていた場合、相続人は妻・子2人・養子である孫2人の5人になりますが、法定相続人の数は、妻・子2人・養子のうち1人(実子がいるため)の計4人となります。
この場合の基礎控除額は3,000万円+600万円×4人で5,400万円となります。
その他、死亡保険金や死亡退職金は、みなし相続財産※といわれます。
生命保険金と退職金は、それぞれ500万円×法定相続人の数までは相続税の非課税とされています。
※民法では相続財産にあたらないが、相続税法上では相続財産にあたる。相続放棄をしていても受取人に指定されている場合は相続税の課税対象で支払いが生じることもある。
1-2. 相続税は誰が納めるのか
相続や遺贈によって財産を取得した人が相続税を支払うことになります。
相続人が複数人いるときにその中の誰かが相続税を滞納している場合、相続税の連帯納付義務に基づき滞納している相続を他の相続人が支払う必要があります。
1-3. 相続税はいつまでに納めるのか
相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヵ月以内が相続税の申告及び納付期限となります。
相続の開始があったことを知った日とは被相続人が亡くなったことを知った日となります。
申告及び納付先は被相続人の居住地の所轄税務署で、通常相続人全員で申告します。
納付は原則現金一括納付になります。期日を過ぎると延滞税等がかかってきます。現金納付が困難な場合、延納や物納などの方法もあります。
2. 相続税の税額計算
プラスの財産-マイナスの財産-葬儀費用が相続税の基礎控除額以下であれば相続税はかかりません。
しかし、
相続人が被相続人の一親等の血族及び配偶者でない場合、相続税額に税額が20%加算※1されます。
第1順位や第2順位がいなかった場合の第3順位の兄弟姉妹や、孫養子※2はこの相続税の2割加算対象者となりますので、ご注意下さい。
※1 相続税負担の調整が目的
※2 孫養子の親が相続時にすでに亡くなっていて、代襲相続人となる場合には2割加算の対象外。
相続税の税額計算をもう少し詳しく説明します。
相続税の計算では実際に相続で取得した財産とは関係なしに、まず遺産総額を法定相続分で分割したものと想定して、相続税の総額を計算します。
法定相続分とは民法で定められています。
配偶者と子供(第1順位)が相続人である場合、配偶者2分の1、子供2分の1になります。
子供が2人以上いる場合は子供全員で2分の1になります。
例えば法定相続人が妻と長男、長女の子供2人のとき、それぞれの法定相続分は妻2分の1、長男4分の1、長女4分の1となります。
配偶者と直系尊属が相続人である場合、配偶者3分の2、直系尊属3分の1となります。直系尊属が2人のときは、直系尊属全員で3分の1になります。
妻・被相続人の父・母(第2順位)が法定相続人のときは、妻3分の2、被相続人の父・母は6分の1ずつということになります。
配偶者と被相続人の兄弟姉妹(第3順位)が法定相続人である場合、妻4分の3、兄弟姉妹4分の1となります。兄弟姉妹が2人以上の場合は兄弟姉妹全員で4分の1になります。
なお、実際の相続は分割協議を行い、合意すれば法定相続分の通りでなくても問題ありません。
相続税の総額を計算する上では、この法定相続分を使用します。
詳しい事例で、計算してみます。
相続財産:現預金・有価証券4000万円
土地等(小規模宅地等の特例適用後):2,000万円
建物:800万円
生命保険:2000万円
未払税金:100万円
葬式費用:300万円
この場合の課税遺産総額は、
プラスの財産-債務-葬式費用-基礎控除額=課税遺産総額ですから、
となります。
法定相続分で相続したものと仮定します。
長男・長女:2,100万円×4分の1=525万円
速算表(後述します)というものがあり、これにあてはめると
長男・長女:525万円×10%=525,000円
よって相続税の総額は
1,075,000円+525,000円×2=2,125,000円となります。
もし実際の分割も法定相続分で行ったとしたら、遺産の取得割合も法定相続分と同様、妻50%、長男25%、長女25%となります。
ただし妻の場合は、配偶者の税額軽減という制度があるので0円となり、妻以外の長男、長女の各自の税額は52万5千円ずつとなります。
相続税の速算表
| 法定相続分に応ずる取得金額 | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 1,000万円以下 | 10% | - |
| 3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
| 5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
| 1億円以下 | 30% | 700万円 |
| 2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
| 3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
| 6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
| 6億円超 | 55% | 7,200万円 |
参考:国税庁「相続税の税率」
実際の分割が法定相続分と異なる場合は、上記で計算した相続税の総額を実際の財産の取得比で按分していきます。
例えば先ほどの相続税が2,125,000円の例でいうと、課税遺産総額2,100万円のうち、妻40%、長男40%、長女20%の割合で遺産を取得したときは下記のようになります。
長男は2,125,000円×40%=850,000円
長女は2,125,000円×20%=425,000円
「節税」に有利な土地活用方法を
ご提案いたします!
あなたの土地・ご希望に合った
複数プランをまとめて比較!
アパート・マンション等の
賃貸住宅や駐車場など、
土地活用をお考えの方はこちら
3. 相続税の計算方法の特例
3-1. 配偶者の税額軽減
配偶者の税額軽減とは、被相続人の配偶者が相続や遺贈により取得した正味遺産額が、法定相続分である2分の1相当額か、1億6千万円までのいずれか多い金額までは相続税がかからない、という制度になります。
先ほどの例でご説明します。
長男は2,125,000円×40%=850,000円
長女は2,125,000円×20%=425,000円
妻は2,100万円の40%=840万円取得しており、正味遺産額が1億6千万円以下のため、850,000円全額が配偶者の税額軽減となります。結果、配偶者の納付するべき相続税額は0円となります。
配偶者の税額軽減は、遺産分割が前提なので、未分割のときは使用できません。
また財産の仮装、隠ぺいされていた財産も対象となりません。
3-2. 小規模宅地等の特例
相続財産は財産評価通達によって評価します。
例えば土地等は倍率方式か路線価方式により評価します。
相続する不動産がある地区が倍率方式か路線価方式かは、国税庁のHPでご確認下さい。
参考:国税庁「財産評価基準書 路線価図・評価倍率表」
上記の財産評価によって計算した宅地等の価額から、減額できる措置として小規模宅地等の特例があります。
相続または遺贈により取得した財産のうちに、その相続の開始直前に被相続人の事業の用に利用されていた宅地等、または被相続人等の居住の用に利用されていた宅地等のうち、一定の選択をしたもので限度面積までの部分については、相続税の課税価額に算入すべき価額の計算上、一定の割合を減額します。
簡単にいうと、被相続人の事務所や自宅、貸付事業として利用していた宅地等は、一定の要件を満たすと、減額される部分があるという特例になります。
ア. 特定事業用宅地等
例えば被相続人の不動産貸付以外の事務所に利用していた宅地等は特定事業用宅地等といい、申告期限までその宅地等を保有していることや、相続人が仕事を引き継ぐなどの一定の要件を満たすと、400㎡まで土地の評価額の80%が減額されます。
イ. 特定同族会社事業用宅地等
被相続人の貸付事業以外の法人の事業に利用されていた宅地等を特定同族会社事業用宅地等といい、申告期限までにその宅地等を保有していることや、取得した相続人が申告期限までに法人の役員になっていることなど一定の要件を満たす場合、400㎡まで土地の評価額の80%が減額されます。
一定の法人とは、相続開始の直前において被相続人と被相続人の親族等が、法人の発行済み株式総数の50%超を所有していた法人になります。
ウ. 特定居住用宅地等
被相続人等の自宅に利用していた宅地等は特定居住用宅地等といい、配偶者が取得した場合は要件なしで適用できます。
被相続人と同居親族は申告期限までその家屋に引き続き居住していることや、その宅地等を保有していることなどの一定の要件を満たすと330㎡まで土地の評価額の80%が減額されます。
自宅とは主として生活の本拠としているところを指しますが、平成26年1月1日以降、2世帯住宅や老人ホームなどに入居していた場合でも、一定の要件も満たせば特定居住用宅地等として取り扱うこととされています。
被相続人と同居していなかった場合で特定居住用宅地等の特例を受けることのできる人は要件がかなり細かいので、国税庁のHPをご確認下さい。
参考:国税庁「相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例」
エ. 貸付事業用宅地等
被相続人の不動産貸付業に利用されていた宅地等は貸付事業用宅地等といい、200㎡までが50%減額となります。
小規模宅地等の特例の限度面積は、特定事業用宅地等と特定居住用宅地等は併用可能のため、最大730㎡となります。
その他は限度面積の範囲内であれば併用可能となりますので、貸付事業用宅地等とそれ以外はあわせて200㎡までとなります。
例えば、自宅120㎡、工場300㎡、不動産貸付用土地100㎡があったとします。
特定事業用宅地等と特定居住用宅地等の要件を満たしている場合、限度面積の範囲内であればどれを選択しても大丈夫です。
ただし上記の例であれば、通常は減額割合が併用可能であり、80%である特定事業用宅地等300㎡、特定居住用宅地等120㎡を選択することが多いと思います。
万が一、1㎡あたりの路線価で比較して、50%減額した不動産貸付用土地の100㎡の宅地等の減額割合が一番大きければ、まず不動産貸付用土地100㎡を使用して、200㎡までの残りを特定事業用宅地等か、特定居住用宅地等から使用するということも可能です。
小規模宅地等の特例は、相続開始前3年以内の贈与や相続時精算課税制度による贈与により取得した宅地等には適用されません。
また未分割の場合にも適用されないので、ご注意下さい。
要件等、詳細については国税庁の説明をご確認下さい。
参考:国税庁「相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例」
3-3. 生前贈与と相続の関係
相続対策の一環で生前贈与をされることもあると思いますが、相続税の計算で、過去の贈与も計算対象となることがあります。
暦年贈与の場合は、相続人に対する相続開始前3年以内の贈与はなかったことになります。
つまり相続開始前3年以内の贈与財産額をプラス相続財産として、相続税額を再計算することになります。
この3年以内の贈与財産に関して、既に贈与税の支払いがある場合には、相続税額から支払った贈与税額を差し引くことができます。
相続時精算課税制度を利用して生前贈与していた場合、もともと相続時精算課税制度は、相続のときに再計算する前提で贈与時に贈与税をかけない制度なので、相続税の計算上、遺産総額に加算する必要があります。
相続開始前3年以内の贈与や、相続時精算課税制度を利用した贈与を受けていた相続人が、分割協議の際に他の相続人に過去の贈与のことを伏せていて、後日相続税額の計算でこれらの贈与があったことがわかると、相続人間でもめることが多いのでご注意下さい。
まとめ
近しい人が亡くなって悲しんでいるときに、いろいろ調べていると10ヵ月はあっという間に過ぎてしまいます。
まずは事前に相続税がかかるかどうかだけでもざっくり計算しておくと、いざというときあわてなくて済みます。
税理士会などでも相続相談を行っているので、気になる方はぜひ専門家に相談してみて下さい。
この記事を監修│専門家プロフィール

-
- 添田 裕美
- 税理士
添田裕美税理士事務所
平成13年税理士登録。税理士事務所において延べ中小企業100社以上に関与。その後独立し添田裕美税理士事務所を開設。
経営計画書作成の支援や決算分析、節税、相続対策など、中小企業経営者の身近な相談役を目指す。
電話でもプラン請求をお受けします。「個人情報の取り扱いについて」に同意の上、お電話ください。


![[19周年]利用者数1,000万人[HOME4U年間利用者数2020年5月現在]](/img/common/header_f1.jpg)













